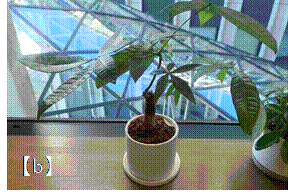相談室だより
|
|
|
|
|
2025.12.26 『ChatGPT とおしゃべり』 最近はChatGPT やGoogle Geminiを身近に使う人が増えてきましたね。私もChatGPT やGeminiも使うようになりました。ごちゃごちゃした頭の中を整理してくれます。「豚肉とレンコンとエリンギ。全然違う味付けで2品考えて。カロリー控えめでお願い」とか「秋冬の黒やグレーなど暗めな服が多いです。テンションを上げる小物のおすすめは?」 こちらの質問があいまいだと「あなたは何を優先したい?」「あなたが大事にしたいことは何?」と聞いてくれます。「そうだった。わたしのことはやっぱりわたしが決めなくては」と気づかされます。 便利な一方で気をつけたいこともあります。AIは質問すると瞬時に反応してくれる分、自分で時間をかけてじっくり考える機会が減ってしまうこともあります。信頼性の乏しい情報も混ざっています。先日は「大人が読みたい絵本」「上高地の格安のグルメなツアー」を検索したら、すごくいい感じの回答「Aツアー」「B本」がありました。予約をしようとしましたがどこを探しても出てきません。AIに<AというツアーもBという絵本も売っていませんよ>と書くと「あなたのおっしゃる通りです。それはありません」「ではCツアー、Dという絵本はいかがしょう」と回答がありました。しれっとしていました。 存在しないことをあたかも存在するかのように堂々と主張する現象はハルシネーションと呼ばれています。情報を得るのは速くなったけれど、間違った情報を鵜呑みにしないようにしようと思いました。 「SNSとの付き合い方をどうするか」「自分の暮らしをどうしたいのか」はやはり自分で決めるしかない部分です。 AIは確かに頼りになる存在ですが、それをどう使うかは使う人の工夫次第です。日々のちょっとしたサポートにAIを活用しながら、同時に「自分の気持ちや考えをどう整理するか」を意識することは大切だなと思います。そして、不安や悩みを抱えたときには、人に話すことでしか得られない安心感や気づきもあります。 AIは日々進化して、共感的に話をきいてくれて迷いや不安を肯定的にリフレイミングしてくれます。でも対話していくと「こうするといいですよ」「やってみたいですか」といった問題解決的な提案が多めです。疲れ切っているときやいろいろ試したけどうまくいかないときもあります。うなづいたり、表情をみながらゆっくりと耳を傾けることもありません。戸惑い、解決しようとしても動けないとき、カウンセラーはことばとことばの間の時間や堂々巡りにも耳を傾け、相手の表情から感じ取ることを大事にしている場所です。たまには人と話してみませんか。瞬時に回答を示すことはできないけれど、相談室でお待ちしています。 (豊橋学生相談室 にしはら) |
||
|
|
||
|
2025.12.22 『笑顔になれるほうへ』 実はこの夏、名古屋学生相談室の植木鉢を一新しました。ここ数年、植物の成長とともに植木鉢が小さくなっていたり、鉢自体が古くなっていたり、土もやせ細っていたりして、非常に気になっていましたが、そのさらに数年前に、土替えをしたところ、虫を発生させてしまい、大騒ぎになってしまったので、その後ますます植え替えに腰が重くなってしまいました。いろいろと言い訳を並べながら、他のカウンセラーさんに相談したところ、「今でしょう!」と背中を押していただき、やっと踏み切ることができました。 今度はちゃんとお店に依頼しようと思い、キャンパスの近くの園芸店に全種類持っていきました。植物の年数を聞かれ、それぞれに合ったサイズの鉢を紹介してもらい、ふかふかの土を入れていただきました。でも、植物自体はもとのままですし、鉢の色も以前と同じ白にしたので、誰にも気づかれず…。室長にご報告したところ、「どこが変わったの?」と言われてしまったほどです(笑)。 ところが、数か月したある日、その青々と生き生きとした姿に、「大きくなったねぇ!」と室長からお褒めの言葉をいただきました!元の写真を撮っていなかったので、Before⇒Afterでお見せできないのが非常に残念ですが、本当に別人のような成長を遂げたのです。少し、ご紹介させてください。
(a) の(おそらく)マザーリーフは、茎が見えてやせていたのですが、鉢からあふれそうなほど生い茂りました。
(b) のパキラは、当初、鉢が大きすぎるくらいでしたが、今や葉っぱが倍以上に大きくなったことで、むしろ鉢が小さく見えるほどです。
(c) のガジュマルは、しばらく変化がありませんでしたが、12月になって急に黄緑色の新葉出てきました。
(d) の(おそらく?)幸福の木は、今のところあまり変化はありませんが、今年も順調に新しい葉が伸びているようです。 植木鉢を変える際は、ちゃんと植物が新しい環境に根付いてくれるか、枯れてしまうことはないかと、心配もありましたが、今となっては本当に変えて大成功でした。やはり環境って大事だなぁとつくづく実感した出来事でした。
私自身は「逃げたら逃げ癖がつく」と言われることがすごく苦手でした。それを跳ね返すだけの自信もなく、未来のことも予測しきれないので、辞めない方がいいのではないか…と悩みがちでした。「AとBと道があったら、しんどい方を進め。成長できるから。」みたいな言い回しもどこかで聞いた気がします。致し方なく方向転換するときも、罪悪感や劣等感、挫折感がありました。 でもあるとき、「笑顔になれる方を選んだらいいよ」と声をかけてくれる人がいて、その言葉は私にとって晴天の霹靂でした。「頑張るか」、「逃げるか」の二択だと思っていたのが、「笑顔になれるか」という選択肢が加わり、肩の力が抜けました。 学生さんの中でも、「成長したいから」とあえて、自分の苦手なタイプのゼミやサークルに入ろうとしたり、苦手な分野への就職活動に挑もうとされる姿を見かけます。それはそれですごくまぶしいことですし、<まだ若いからそれもありかも!>とも思うのですが、一方で、<あなたにはあなたにしかない良さがあるんだから、それを大事にして、そのままのあなたが輝ける環境もあると思うんだけれど、どうかな…>と内心では思ってしまうのです。 人生は一度きり。本当に自分は何が好きで、どんなことに幸せを感じるのか、何を大事にしたいのか、何をするのが辛くて、何は不自由なくできるのか…。人生最後の日に、 「これでよかった」と笑顔でいられたらいいなと思います。 何の話だか、よくわからなくなってしまいました(笑)。 今年も一年、皆さん、本当にお疲れ様でした!良いお年をお迎えください。 名古屋学生相談室 五藤 |
||
|
|
||
|
2025.11.26 朝晩の冷え込みが一段と増し、キャンパスの木々もすっかり冬支度を始めています。レポートや試験、ゼミ発表などに追われ、気がつけば「休む予定」だけが後回しになっている人、いませんか? 心身の疲れは気づかないうちに溜まりがちです。お風呂にゆっくり浸かる、温かい飲み物を味わう、目を閉じて深呼吸をする――そんな小さな休憩時間を一日のどこかに意識的に組み込んでみてください。 もし,眠れない日が続く、友人と会うのがおっくうで授業に向かう足が重い、涙やイライラが止まらない、といった状態が二週間以上続くなら、それはひとりで抱え込まないほうがよいサインです。学生相談室は病気かどうかを判定する場所ではなく、いっしょに状況を整理し、これからの大学生活をより良くするように考えるためのスペースです。どうぞお気軽にお越しください。 (この文章はChatGPT 5.1 Thinkingの草稿を元に石塚が作成しました) 名古屋校舎 精神科医 石塚佳奈子 |
||
|
|
||
|
2025.11.07 『本は効率の良い情報収集ツール?―あらためて本のススメ』 突然ですが、私はブログがちょっと苦手です。今まで興味あるテーマが出てくると、いったんは、ネット検索をかけて、そのテーマを扱っているブログを読んでみようとトライはしてみました。…でも挫折してしまうのです。それはなぜか考えてみると、私にはブログは、情報がバラバラに並んでいて、どこから手をつけていいか分からなく感じられるからなのです。もちろん多くの場合、記事はちゃんとテーマごとに分類されています。でも基本的には、発信者がその時発信したいことをランダムに投稿していく作りになっているかと思います。そのため、例えば「ミニマリスト」が何かざっくり知りたいと思い(実は一時期ミニマリストに興味持ってました)、それっぽいタイトル(「例:私がミニマリストになったワケ」)を探して読む、でも知りたい事の一部ではあったけどなんかちょっと違ったと感じ、また別の記事を読む…。それを何度も繰り返してやっと「ミニマリストって要はこういうことらしい」と見えてくるという感じ。ちょっと時間つぶしに何か読みたい、という時にはそれでも全然かまわないのですが、あるテーマの知識を仕入れたいと明確な目的がある時にはちょっともどかしく感じます。 ここで本のススメです。本の場合、情報が系統立てて並べられています。序章では、本の内容がおおまかに説明されて、第一章では、扱う概念の定義を述べてくれる場合が多いです。先の例であれば、「ミニマリストとは何か」ですね。これって、実はすごいことなんじゃないかと思うのです。私のイメージでは、情報探索の旅にちゃんと地図がついている感じ。本の場合“目次”が地図にあたります。目次を見ると、どういう順番でどんな情報が提示されるのかある程度わかるので、自分の位置を確認しながら進めます。一方ネットでの情報収集は、地図がないまま、カンを頼りに広大な世界に歩き出す感じ。出会う情報が自分の頭の中の「知りたい世界の地図」のどこに当てはまるかをいちいち判断しながら、パズルのピースを組み立てるみたいに地図を完成させていくイメージです。さらに、ネットの場合、情報の質が玉石混交なので、「信頼できる情報か」「発信者は専門家なのか」なども同時に判断しなければいけません。これって結構大変な作業なんじゃないかと個人的には思います。一方で本の場合、編集作業というフィルターがかかっているので、情報の正確さは(ある程度)確認されているし、著者はたいていその分野の専門家なので、100%の信頼は難しくても、ある程度安心して読むことが出来ます。あと、これはオマケ的なところですが、本って物理的に残りページ量が見えるので、今自分はこのテーマについて7割くらいの情報を得たな…と自分の位置を確認できるのも良いなと感じています。さらに、一冊読み終わればある程度は情報を得たような感じがして、“終わり”がある感じもいいですね。ネット検索って、時にずーっとやり続けてしまいますもんね…。 というわけで、もしかして時代に逆行しているのかもしれませんが、情報を集める方法として、本はなかなか効率的かもしれない、というお話でした。 名古屋学生相談室 梅村 |
||
|
|
||
|
2025.11.05 『星空の向こうの生命』 太陽系の惑星を見てみると、やっぱり地球はすごく特別ですよね。なによりも、大量の水があるからこそ、ほかの惑星とは一味違う存在感があります。水は多くの物質を溶かすことができて、その中から“生命”が生まれたと考えられています。そのため、生命は地球だけにしか存在しない特別な現象、と考えられてきました。でも最近の宇宙探査で、土星の衛星や火星、さらには月の地下にも液体の水があるかもしれないことがわかってきたんです。こうした天体にも生命がいるかもしれない、そんな期待がどんどん広がっています。 学校で習う生物の授業は基本的に地球の生命しか扱いません。言わば、“地球生物学”ですね。でもここ数年は「宇宙生物学(Astrobiology)」という言葉もよく聞くようになりました。宇宙全体で生命がどうやってできたのか、地球以外にも生命は存在するのかを探る学問です。もしかしたら地球外で生まれた生命が地球にやって来て進化したのかもしれません。SF映画の話だったことが、今やれっきとした科学の研究テーマになっているんです。実際、小惑星探査機はやぶさ2が持ち帰った試料からは、生命の基礎となるアミノ酸も見つかっています。 こうした研究は理学という分野に含まれます。理学は法律や経済、経営のように社会の役に立つためだけの学問ではありません。宇宙生物学を勉強してもすぐにお金儲けや社会問題の解決には結びつかないかもしれませんが、このようなロマンに満ちたテーマに触れることで、間違いなく心が豊かになります。大学は、明日役に立つことだけでなく、人生のどこかで深く役立つかもしれないことを学ぶ場でもあります。資格やスキルも大事ですが、そればかりに縛られすぎて疲れてしまうのはもったいない。たまには夜空を見上げて、「このどこかに生命はいるのだろうか」と想像してみるのも悪くありません。 経営学部 古川 邦之 |
||
|
|
||
|
2025.08.29 『ゼミ生同士の結婚』 愛大名古屋キャンパス近くのストリングスホテルで今年の6月に披露宴がありました。今回の披露宴はゼミのOB同士の披露宴、卒後6年目の女子と5年目の男子の結婚です。ゼミ生同士の結婚は今回で14組目となります。 初めてゼミ生同士が結婚したのは30年ほど前、ゼミの6期生同士の結婚でした。この二人がお付き合いしているのは彼らが学生の時から知っておりましたが、まさか人生で一番重要な結婚にまでいたるとは考えてもいなかったので、最初に結婚しますと連絡を受けたときにはびっくりしたものの、そうはいっても若い男女が集うのだから中には恋に発展することもあるのだろうなあと。 しかしその後、ほぼ毎年のように結婚するゼミ生同士が出てきて、あれよあれよという間に10組目のカップルが誕生し、これは定年までに15組ぐらいになるのかなと思っていたら、まさにそれが現実のものとなりそうな気配です。まさかゼミで出会って結婚にまで発展することがこれほどあるとは。 ちなみに14組のうち、同じ学年が9組、そして学年違いが5組です。今回も学年違いの組み合わせでしたが、この子たちがゼミ生だった時にはまだコロナが始まっておらず、両学年合同で夏や春にゼミ旅行をしたり、食事会・飲み会もいつも合同でしていましたので、それで自然に仲良くなっていったようです。 こういう学年違いのカップルの披露宴に招待されて楽しいことの一つは、数多くのゼミのOB達と会えることです。今回も、両学年合計16名が来ておりましたので、なんだかミニOB会のようで楽しかったです。また披露宴が終わったあとは、大学の本館研究棟20階のラウンジに場所を移し、新郎新婦を含めて2時間ぐらいワイワイと歓談し、実に楽しいひと時を過ごすことができました。 そうこうしていたら先日、卒後5年目の男子と4年目の女子が婚約しましたという連絡があって、退職まであと2年半、それまでに少しきりの良い15組目が誕生することが確実になったしだい。めでたしめでたし。 経済学部 沈 徹 |
||
|
|
|
|
|
2025.07.31 『ソーセージと木漏れ日』 私はドイツ語を学び始めてかれこれ20年になります。ドイツ語を勉強していて楽しいと感じるのは、ドイツ語で人と意思疎通ができるようになった時。ですが、それ以上にもっと楽しいのは、ドイツ語の面白い表現や言葉に出会った時です。ドイツ語に限らず、あらゆる言語に共通することですが、言葉というものは文化の一部であり、むしろ文化そのものであると考えます。 例えば、ドイツと言えばソーセージを思い浮かべる人も多いかと思いますが、ドイツにはソーセージ(Wurst)を使った慣用句がたくさんあります。「Das ist mir Wurst」は直訳すると「それは私にとってソーセージだ」ですが、「それは私にとってどうでもよいことだ」という意味で用いられています。「Es geht um die
Wurst(それはソーセージに関するものだ)」は、試合などの「とても大事な局面」を意味します。ドイツの食文化にとってソーセージが欠かせないものだったために、こうした慣用句が生れたのですね。単語に関していうと、私のお気に入りのドイツ語は「Zugenbrecher」と「Hexenschuss」です。「Zugenbrecher」はZunge(舌)+Brecher(クラッシャー)の複合語「舌のクラッシャー」で、「早口言葉」という意味。「Hexenschuss」はHexe(魔女)+Schuss(射撃)=「魔女の射撃」で、「ぎっくり腰」という意味です。面白い表現をするな、と笑ってしまいます。一番素敵だと思うのは「Schneewesen」という言葉。Schnee(雪)+Wesen(箒)=「雪ほうき」で、「泡立て器」の意味です。泡立て器でメレンゲを作るときに、それを雪に見立てて生まれた言葉なのだと思います。なんて綺麗な言葉なんだろうとため息をついてしまいました。 ドイツ語を学んでいていると興味深い言葉や表現に出会うのですが、日本語の素敵な表現を発見することもあります。例えば、「木漏れ日」という言葉。木の枝葉から差し込む日の光のことです。「木漏れ日」を一言で表す言語は、日本語の他にはないそうです。こんな自然の美しさに名前を付けた人はなんて繊細な言語感覚を持った素敵な人なのでしょう。 木漏れ日の中で森林浴を楽しみたいところですが、暑すぎて外出できませんね。冷房の効いた部屋に引きこもって、この文章を書いています。毎日暑い日が続きますが、みなさんもどうか体調など崩されませんよう、ご自愛ください。 国際コミュニケーション学部 樋口
恵 |
||
|
|
||
|
2025.07.26 『相談室だより』 毎朝、大学までの通勤に、私は名古屋市営地下鉄鶴舞線「平針」駅で乗車し、「大須観音」駅で下車し、笹島校舎まで歩いています。 十年前からでしょうか、「平針」駅二番出入口までの約一〇分間の歩行中に、一つの現象が続いていることに気が付きました。それは、出入口の約二〇〇メートル前から、ほぼ総ての通勤通学客が歩道の左側を歩いていることです。一つの理由は、目指す出入口が向かって左側に位置しているため、人々は、少しでも早く着こうとしているのでしょう。もう一つの理由は、地下鉄「平針」駅構内が左側通行になっており、地上に出てくる大半の人々がそのまま惰性で歩道の左側を歩いてくるからでしょう。 一〇年前には、こうした現象は極めて稀でした。現在では、通勤通学ラッシュ時以外の時間帯でも、左側通行が常態化しています(ちなみに、私の場合、地下鉄出入口までは、歩道の右側を歩いています。そうしますと、前方から左側を歩いてくる人々とは、正面衝突することになります。これを避けるため、空いている方の手を挙げて、合図をし、かつ軽く会釈して、右側通行を続けています)。こうした毎朝の通勤通学時の光景に、現代社会が世知辛くなっているように私は感じています。 近時、教育・社会学研究者の桜井智恵子さん(現在、関西学院大学人間福祉学部教授)へのインタビュー記事「しんどさ増す子ども」(二〇二五年七月一五日付朝日新聞日刊第一一面掲載「オピニオン&フォーラム」欄、聴き手は田中聡子記者)を拝読しました。学力をつけて競争社会を勝ち抜かないと将来「食べていく」ことができないという風潮が家庭レベルにまで浸透した結果、「子どもが壊れ」始めていると、桜井さんは警鐘を鳴らしています。そして、桜井さんは、競争しなくとも、「みんなが食べて」いくことができる社会にすることが必要ではないか、とも指摘しておられます。 大学は、しばしば「象牙の塔」と揶揄されることがあります。しかし、大学も、社会を構成する一組織です。そして、毎年、卒業生を社会へ送り出し、入れ替わりに新入生を迎えています。教員の場合も、定年で退職者が出ると、担当科目次第では、後任者が補充されます。このように人の出入りがある以上、大学内にも現代社会の様々な風潮が入ってきます。 おそらく、この拙文をお読みなっている学生の皆さんは、朝晩の通学ラッシュに辟易し、日頃の大学構内でも息苦しさを感じておられるからではないでしょうか。学生相談室では、専門相談員(臨床心理士・公認心理士)が交代で常駐しています。学業絡みの悩み事であれば、私をも含めた各学部からの専任教員が、対応します(私の場合、四月から相談員となりました。しかし、かなり以前に当相談室の関連部局である学生部委員会という組織で、学生面談の経験があります)。皆さんから相談された内容について、私どもは秘密を厳守します。どうぞ気軽に相談室を訪ねてみて下さい。 法学部 大川 四郎 |
||
|
|
||
|
2025.06.10 『春と夏の間に梅雨がある』 季節の変わり目ですね。寒かった冬はやっと終わり、春が来たと思ったら、夏が見えてくる。 夏が見えたと思ったら、またすこし肌寒い春のような気候に戻り、季節が移り変わっていく。もう夏が来たのかと思えるほど、気温が上がるのが今年の特徴と言えるのではないでしょうか。 近所の子どもが、題名にある通り、春と夏との間には梅雨があるんだよと、あたかも5番目の季節があるかのように話していました。そうとも言えるほど、梅雨の時期は、独特の気候がありますね。愛知もそろそろ梅雨になるようです。カラッと晴れ、肌がジリジリくるような夏はまだまだ先ですね。 学生の皆さんにとっては、そろそろ授業に慣れてきたころでしょうか?授業の中間課題が出て、四苦八苦しているかもしれませんね。初めて書くレポートに困っている方もいるかもしれません。 5月、6月は移り変わりやすい気候のせいもありますが、4月からの新生活に向けて、緊張状態だった時期を通り越して、なんとなく慣れてきて緊張感が薄れるときです。人の体は不思議なもので、そういう時に風邪を引くなど、体調を崩すことがあります。なんだかだるい、疲れが取れないと思うのも、新一年生は受験期から含めた長い間の疲れがたまっているせいかもしれません。在学生の皆さんも、2年目以上の学生生活経験があったとしても、春学期は緊張感があるものではないでしょうか。緊張は、すぐ解ける人もいれば、そうでない人もいて、個人差があります。 体調の悪さ、眠れない、起きられない、といった症状がでてくるのも、梅雨が始まるこの時期が多いように思います。 そんな時は、まず休むことが大切だと思っています。しかし、そうできないことも多いですよね。多くの方は時間が過ぎれば体調も戻ってきて、大学での生活も慣れたと思える時が来ると思います。しかし、なんとなく体調が戻らない状態があり、それはなぜかなと思ったときは、誰かに話をしてみてください。他人の考えを聞くと、一緒の悩みを抱えていたことに安心したり、気分転換になるような新しい方法を知ることになったりと、自分だけでは思いつかなかった事が分かる場合もあります。 誰かに話すことは勇気がいると思っている方には、相談室があることをお忘れなく!いつもの関係性の中では話し辛いことも、第三者視点でカウンセラーとは相談ができると思います。一対一の個室での対応となりますので、安心して、相談に来てください。 豊橋学生相談室 長坂 |
||
|
|
||
|
2025.05.26 『片付けから心を考える』
はじめまして。4月から新しく車道キャンパスの学生相談室の非常勤相談員になりました、沢出 友美です。 私は、1年ほど前から“お片付け動画”にはまっています。自分の家を快適に整えたいと思ったことがきっかけですが、今では片付けをきっかけに人が変わっていく様子に惹かれ、人間ドラマとして見ていると言ってもいいかもしれません。 なかでも、断捨離の提唱者やましたひでこさんと、捨てなくてもいいというスタンスの整理収納アドバイザー古堅純子さんの番組や動画をよく見ているのですが、“捨てる派”のやましたさんと“捨てない派”の古堅さんが両極にいるように見えて、依頼者には共通して『今』を大事にしましょうというメッセージを送っているところがとても興味深いなと感じています。 やましたさんは、過去の思い出や未来への不安からたくさんのものを抱え込んでいる依頼者に、それは本当に『今』のあなたに必要なもの?と問いかけます。古堅さんは、部屋の中の景色を良くして、『今』使うものを使いやすい場所に収納していくために、その家に暮らす人が『今』大切にしたいことをヒアリングしながら片づけを進めていきます。 すると、やましたさんの依頼者が今の自分に不要なものを手放していくだけでなく、古堅さんの依頼者も今使わないものにスペースを取られてしまうことをもったいないと感じ、ものを減らす方向へ進んでいくことが少なくありません。 頭や心の中も同じように、過去の出来事にとらわれすぎてしまったり、まだ起きていないことへの心配で押しつぶされてしまったりして、今に目を向けることが難しくなることがあります。そんなとき、過去を振り返って整理し、未来をほどよく考えながら、今の自分はどうしていこうかを見つけていく一つの方法として、学生相談室を利用してもらえたらいいなと思っています。
車道学生相談室 沢出 |
||