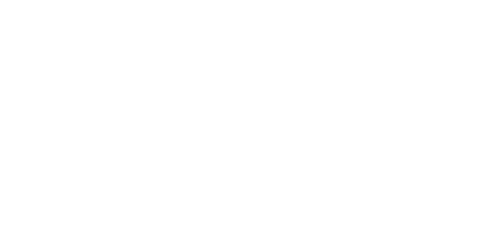
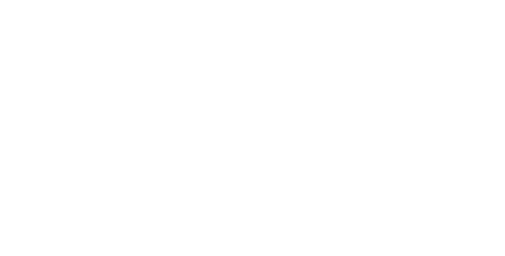
講 義 「近 代 経 済 思 想 史」
(昼間部,春 学 期, 2単位,3年次生以上履修可能)
〇 講義のテーマ;「自由主義,歴史主義,および社会主義の経済思想の歴史」
〇.今期の講義の概要
経済的自由主義,歴史主義および社会主義の経済思想の歴史を概説する。
Ⅰ.経済的自由主義(Economic
Liberalism,Liberalismus,lib ralisme)
1.定義(一例)
「経済活動を調整するために,市場と競争の力を最大限に利用することを擁護する学説
それは,国家には,市場が提供できないような活動,すなわち,公共財の供給,あるいは
例えば所有と契約に関する法的枠組みの樹立や反独占法のような政策の採用によって,私
的市場経済が効果的に機能しうるための枠組みを作り上げるために必要な活動のみを認め
る。」(『現代経済学辞典』マクミラン社,1983年,123頁)。
2.経済的自由主義にたつ学説
A.イギリス古典経済学・・・アダム・スミス,デーヴィット・リカードウ,J.S.ミル
B.ケンブリッジ学派(新古典派)・・・アルフレート・マーシャル,ヒックス,
C.オーストリア学派・・・・カール・メンガー,ボェーム=バウェルクなど。
3.特徴
A.経済的自由主義は,市場における経済主体の自由な競争を通じて,資源と労働力の
配分,生産と消費との調整などを行うとする思想
B.市場において自由競争を行う経済主体は,自分の資本や土地や労働力についての自
由な処分権をもつ──→私有財産権の承認。
C.国家による経済に対する保護や干渉の政策を否定──→国家は,市場メカニズムが
発揮しやすいように,経済主体の自由競争を保障するような活動をする。
D.自由競争,自由貿易,安価な政府などの主張
Ⅱ.歴史主義 (Historicism,Historismus,historisme)
1.定義(一例)
「歴史主義とは,歴史における発展を強調し,歴史における個性を重要視し,われわれ
の思考を歴史的にする思想上の立場である」(『哲学事典』平凡社,1954年,1268頁)。
2.歴史主義にたつ学説
ドイツ歴史学派 (Historical School,Die Historische Schule)
旧歴史学派・・・ヴィルヘルム・ロッシャー,ブルーノー・ヒルデブラント,カール
・クニース
新歴史学派・・・グスタフ・シュモラー,ルヨ・ブレンターノ,アドルフ・ワグナー後期
歴史学派・・マックス・ウェーバー,ウェルナー・ゾンバルト
歴史主義は,経済学以外にも見られ,ドイツの歴史法学派やヘーゲル哲学にも見られる
また,マルクス学派や制度学派の学説の中にも,歴史主義的な見解がみられる。
3.特徴
A.経済組織や制度の歴史的な発展を強調する。
B.組織や制度の評価において,歴史的な相対主義の立場をとる。
C.世界経済ではなく,国民経済の発展を捉えようとする──→経済発展段階論の提唱
D.経済現象をそれをとりまく社会現象(法や国家や集団)),文化現象(イデオロギ
ー,宗教,思想)と関連づけて捉える──→経済の自律的法則を認めない。
Ⅲ.社会主義 (Socialism,Sozialismus,socialisme)
1.定義(一例)
「この用語は,生産手段(資本と土地)の所有と統制が,全体としての共同社会によっ
てなされ,全体の利益にもとづいて管理されるべきだとする,一般的な学説を述べるため
に用いられる。マルクスの社会主義にとっては,社会主義とは,資本主義の共産主義への
不可避的な移行の際の中間段階である。社会主義国家は,プロレタリアートの独裁と希少
性の存在という特徴を持っている。・・・・[マルクス主義者以外の]多くの社会主義者
にとっては,社会主義とは,本質的には資本主義的構造を保持する社会改良の計画を意味
している。しかも,多くのものにとっては,社会主義は計画経済と同じ意味である。」
(『現代経済学辞典』マクミラン社,1983年,407頁)。
2.社会主義にたつ学説
A.初期社会主義・・・ロバート・オウエン,シャルル・フーリエ,サン・シモン
オーギュスト・ブランキ
B.マルクス主義・・・カール・マルクス,フリードリヒ・エンゲルス
カール・カウツキー,ルドルフ・ヒルファディング
ローザ・ルクセンブルク, V.I.レーニン,河上肇,
C.社会改良主義・・・ルイ・ブラン
シドニー・ウェッブ,ヴェアトリス・ウェッブ
フェルディナンド・ラサール
エドゥアルト・ベルンシュタイン
ヴァイマル共和国期および第二次大戦後の社会民主主義者
D.福祉国家論・・・・ミュルダールなどスウェーデンの社会民主主義者
ストレイチーなどイギリス労働党の理論家
3.学説の特徴
A.個人よりも共同社会を重視する──→個人の自由で利己的な活動に対する社会の規
制の承認。
B.マルクス主義とその他の社会主義との間に,大きな相違がある。
マルクス主義───生産手段の私的所有(私有財産制)の廃止
社会改良主義───私的所有の弊害を社会の力により是正しょうとする。私的所有
の活動に対する社会的な制限。
C.マルクス主義は,生産手段の所有形態に由来する階級対立と階級闘争を歴史発展の
基本動因とみる。(階級闘争史観)。
D.市場経済と私有財産制への批判──→市場経済を計画経済に置き換えるか,市場経
済と計画経済の結合を提唱。
E.民衆の利益に沿った,国家による社会や経済への干渉・管理を承認する。
第 一 部 経 済 的 自 由 主 義 の 思 想
Ⅰ.自由主義・民主主義の思想の源泉
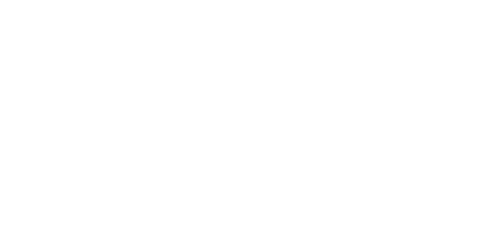
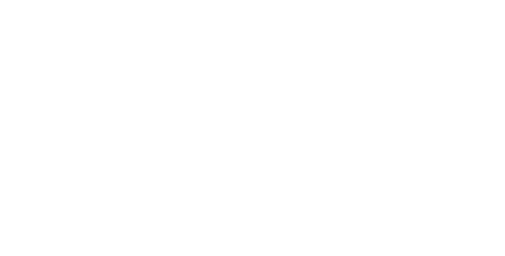
Ⅱ.経済的自由主義の思想(1)───古典学派の経済的自由主義───
1.アダム・スミス(Adam Smith,1723-1790)
・イギリスの重商主義思想やフランスの重農主義学説を踏まえて,自由主義の経済思想
を提唱し,経済学の父と言われる。イギリスの産業革命とともに勃興した製造業の資
本家の思想を代表している。
・主著;『道徳感情論』(1759年),『諸国民の富』(1776年)
A.自由主義と利己主義との相違
・人間の本性・・・利己心と同感の感情作用
・公平な事情に通じた第三者の同感──→道徳と法の基礎
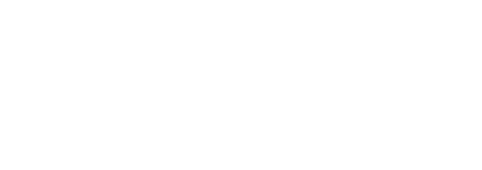
C.経済人の利己心の肯定
・利己心に従う経済活動─→分業の発展─→生産力発展─→階級差別にもかかわらず
富裕が底辺まで広がる。
D.市場経済論の提唱
・自由な商品交換=市場メカニズムの重視←──→重商主義の保護主義
E.資本蓄積論の解明
・資本家の節約=貯蓄による資本形成と投資→生産的労働の増大→国富の増大
F.自由主義的な国家観
・安価な政府論(治政・国防・公共事業が政府の仕事)←──有用労働・不生産的労働
G.自由主義的政策思想
・自由放任(自由競争)・・・自由な経済活動,政府は不干渉。
・自由貿易 ・・・関税などによる保護貿易の廃止。
・均衡財政思想 ・・・歳入に見合った歳出による健全な財政状態の保持。
2.ジェレミー・ベンサム Jeremy Bentham (1748-1832)
・イギリス功利主義哲学の代表者。哲学的急進主義(功利主義哲学に基づく民主主義)
・功利主義の定義;
「行為の価値基準が快楽=幸福の増大と苦痛=不幸の減少にあるとする倫理学説であ
る」(永井義雄)。「功利の原理つまり快苦原理により公共の利益を保障」。
・主著;
『道徳および立法の原理序説』(An introduction to the principles of
morals and
legistlation,1789)
A. 合理的刑法体系の基礎理論としての功利主義
量刑の決定のためには, 快楽も苦痛も計算可能なものと取り扱われた。
幸福計算(快苦計算)の可能性を前提。
B.個人の自由な幸福追求を承認し,かつ最大多数の最大幸福の実現を目指す。
自由と諸個人の間の調和との両立を目指す。
C.自然権と自然法を否定し,制定法の地盤にたった
法体系と司法制度の徹底的合理化を図った。
快苦原理による量刑の確定(制定法主義)。
・『高利擁護論』(Defence of Usery,1787)
利子率の上限を法律で定める必要はないと主張(スミスより徹底した自由主義)。
・賃金基金説(労働者の平均賃金は資本量と労働者数とに左右される)の主張。
失業者の救済は国家の役割とする。
3.ジョン・スチュアート・ミル John Stuart Mill(1806-1873)
・イギリス古典経済学の再編者。歴史主義,社会主義と対決し,分配社会主義の思想を
提唱。婦人参政権や土地制度改革の運動にも参加。
・功利主義の立場に立つ。
個人の自由な幸福追求の承認+最大多数の最大幸福。各人の自由と諸個人間の調和と
いう課題は,解決可能。ミルは各人の快楽に質的相違を認める点でベンサムと異なる
・主著;
『経済学原理』(Principle of Political Economy,with some of
their applications
to social philosopy,London 1847)
A.リカード経済学を継承。ただし,価値論は労働価値説でなく,生産費説に立つ。
資本主義生産に確信をもつ。
B.資本主義生産のひずみ=富の分配上の不平等を洞察─→公平な分配(分配的正義)
を主張──→国家の介入=累進課税・高率相続税・土地私有の廃止(地代収入の国有
化)等の手段を提唱──→後の福祉国家(国家財政による社会保障)への展望。
『自由論』(On Liberty,1859)
A.個人の活力や個性の価値を強調。
B.財産集中の排除と競争の刺激により人々の勤労意欲を惹起させる。
C.人間性の進歩を可能にする回路の設定。
Ⅲ.経済的自由主義の思想(2)──限界効用学派の経済的自由主義───
・限界効用学派のオーストリア学派,ケンブリッジ学派
・新古典派(ケンブリッジ学派の流れを汲む英米の経済学)
1.アルフレッド・マーシャル Alfred Marshall (1842-1924)
・イギリスのケンブリッジ学派の創設者。
・ダーウィンの進化論やJ.S.ミルの功利主義の影響を受ける。
・スミスやリカードゥの古典経済学の「現代的改訳」を試みた。
・ミクロ経済学を作った。
・主著;
『経済学原理』(Principles of Economics,an introductory
volume.London 1890)
A.生産費説を保存しつつ,受容の側面を限界効用価値説によって補強した。
生産費=主要費用(原料・直接労務費・設備の磨滅部分)+補足的費用(設備の使
用に基づかない減価・資本利子)
生産物の価値は,短期的には限界主要費用を中心に動くが,長期的には主要費用と
補足費用を含む総費用によって決定されるとみた。
B.つまり短期と長期という時間的要素を,経済学に導入した。
C.賃金論
生存費説を取らず。資本蓄積と技術進歩によって生ずる労働の需要価格の上昇が,
企業間の競争を通じて,賃金上昇をもたらすとみた。
持続的な生活水準の上昇と労働者の資質の向上──→労働生産性の上昇の可能性
D. 外部経済と内部経済,代表的企業,需要の弾力性などの新概念の提出。
2.カール・メンガー Carl Menger (1840-1921)
・オーストリア学派の創設者。
・主著;
『国民経済学原理』(Grundsaetze der Volkswirtschaftslehre,Wien
1871)
A.第一部のみ出版され,第二部は構想のみ。
ワルラス,ジェヴォンズとともに,限界効用価値論を発見。
B.価値論=限界効用価値論 (限界効用逓減法則,限界効用均等法則)
・帰属理論の原型を提出
・消費財の価値は,最終単位の効用の大きさによって決まり,生産財の価値は,それに
よって作られる消費財の予想価値によって決まるという見解。
(生産財の価値←───消費財の価値←───最終単位の限界効用)
C.人間の欲望とその充足手段との因果関係の解明
─→さまざまの財の補完性に注目
D.時間要素の役割の重視。
Ⅳ.経済的自由主義の思想(3)───現代の経済的自由主義───
1.ジョゼフ・アロイス・シュムペーター(Joseph Alois Schumpeter,1883-1950)
・オーストリア学派の継承者のひとり。グラーツ大学,ウィーン大学,ボン大学などで
教鞭をとったが,1933年にアメリカへ移住し,ハーバート大学の教授となり,多くの
研究者を養成。近年,ケインズに対抗するその理論が見直されている。
・著作;
『理論経済学の本質と主要内容』(1908)
『経済発展の理論』(1912)
『景気循環論』(1939)
『資本主義・社会主義・民主主義』(1942)
『経済分析の歴史』(1954)
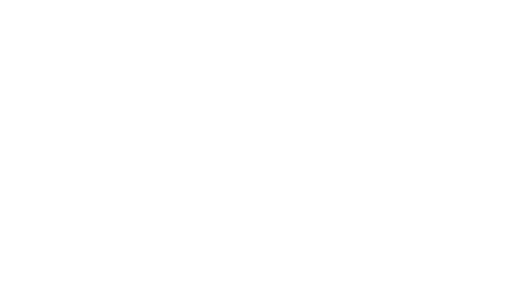
(2) 静態的経済と動態的経済の区別
・静態的経済の特徴
通常は,同じ規模での経済の進行のことを静態というが,シュムペーターの場合,同じ
技術水準で生産規模が増大する場合も,静態と考えている。
・動態的経済の特徴
(1) 資本家および企業者(企業家,entreprneur)の存在。
(2) 企業者利潤および利子の存在。
(3) 費用財の中には,労働用役と土地用役以外に,資本用役がある。
(4) 景気変動,恐慌がある。
シュムペーターの動態においては,経済発展は内的な要因によっておこなわれる。
その内的要因とは,企業者によるイノヴェーションの遂行ということである。また
土地用役や労働用役そのものにおいておこなわれる変化の結果としての経済発展も
動態と捉えられる。
・企業者・・・新結合を行うもの。従来通りのやり方に従うものは,「経営者」であり
「企業者」でない。
・資本家・・・企業者に資金を供給するもの。
・信用/貨幣信用・・・生産手段市場において,循環している生産手段を奪うもの。旧
結合の生産から生産手段を奪い,新結合に役立てるための手段。
・銀行・・・・信用創造を行うことにより,企業者に貨幣信用を提供するもの。
B.社会学的な体制移行論
『資本主義・社会主義・民主主義』(1942)
・「資本主義は,その失敗でなく成功によって,社会主義にとってかわられる」という
逆説的な命題の提唱。
・この命題の経済学的根拠
資本主義の発展→大企業と独占組織の発生→その管理業務は社会主義の計画経済に
ちかずく。
・資本主義経済と文化的・社会的・政治的要因との関連まで言及し,総合的に資本主義
体制を解明しようとした。資本主義は,失敗(崩壊)によってではなく,成功によっ
て社会主義へ転化すると主張した。(社会学的文明論的体制移行論)。
・ヒルファディングやV.I.レーニンの資本主義崩壊論との相違。
2.フリードリヒ・ハイエク (Friedrich August Hayek,1899-1992)
・オーストリア学派の後継者,1950年以後,シカゴ大学へ移り,シカゴ学派を創始。
フリードマンともに,新自由主義の代表者。景気循環論の研究および社会・経済制度
の比較研究の業績にたいしてノーベル経済賞を受賞。1967年,ザルツブルク大学教授
・著作;
『貨幣理論と景気理論』(1929),『物価と生産』(
1931),『集産主義的経済計画』
(1935),『個人主義と経済秩序』(1948),『隷従への道』(1944)。
A.市場の擁護
(1) 合理主義批判・・・市場を人間の意識的人為的な管理によって合理化することが望
ましいという見解を批判。むしろ,市場はさまざまの個人の相異なる目的を達成する
共通の手段。
(2) 新古典派の完全情報の前提の否定──→局所的知識の有効利用(断片的知識を価格
シグナルという情報を通して社会全体として利用できるようにする)の提唱。
(3) 新古典派の完全競争の前提の否定・・・市場は競争過程を利用する──→正当な競
争の結果として生じた独占企業は,最も優れた企業として認める。
B.ケインズ批判
(1) ケインズは,総雇傭量や総需要量といった集計概念のみに注目し,生産財と消費財
との相対価格や生産部門間の構造的差異を軽視→誤った経済運営をもたらすと批判
(2) 伝統や慣習を否定し社会正義を主張するケインズは,新古典派とおなじ合理主義・
功利主義の誤りを共有していると批判。
(3) 福祉国家を提唱するケインズの思想には,「法の支配にもとづく自由主義」の立場
に正当な位置が与えられていないと批判。
第 二 部 歴 史 主 義 の 経 済 思 想
Ⅰ.ドイツ歴史学派の展開とその学説の特徴
(出口勇蔵編著『経済学史入門』有斐閣の「2-7歴史学派」を参照)
1.歴史学派の先駆者
A.歴史主義の前提となった事実
・自然法思想にたつ啓蒙主義思想の普遍主義への反省。
・アメリカ独立革命やフランス大革命などの歴史的事件による歴史感覚の覚醒。
・先発資本主義国イギリスと後発国ドイツとの発展水準の相違。
B.歴史主義の特徴
・普遍的法則による説明でなく,それぞれの地方や国家の特殊性に注目。
・個人よりも,集団や民族などの動向に注目。
・歴史的な発展段階を区別し,各国をそのいずれかの段階に位置づける。
C.代表者
(1) ユストス・メーザー(Justus M ser,1720-1846)
・国民生活の日常事について詳細な記述。政策的見解としては高度な分業に反対。領邦
国家の権力に対して小規模経営と貿易商人の擁護。
・著作;『オスナブリュックの歴史』1768,『愛国者の幻想』1774-86。
(2) フリードリヒ・リスト(Friedrich List,1789-1846)
・ドイツ関税同盟の思想的創始者。国民主義的経済思想を述べ,歴史学派の源流となる
チュウビンゲン大学教授。1819年ドイツ商工業同盟を設立し,対英保護関税政策の実
現によるドイツの経済的統一を図るが,挫折。その後,アメリカにわたり企業家とし
て成功するとともに,経済学を研究。1932年に帰国し,ドイツ鉄道網の建設に努力し
た。領邦権力とユンカー(土地貴族)に対抗し,商工業ブルジョワジーの立場に立つ
・主著;『アメリカ経済学概要』1827年。『政治経済学の国民的体系』(1841)。『農地
制度,零細経営,および国外移住』1842年。
2.旧歴史学派
A.歴史学派の生成
(1) ヴィルヘルム・ロッシャー(Wilhelm G.F. Roscher,1817-1894)
・ゲッチンゲンおよびライプチッヒ大学教授。歴史法学派のサヴィニーの歴史的方法の
経済学への適用を提唱。経済学は国民経済の歴史的発展法則を解明するものと見た。
その歴史的方法には生物学的傾向を伴う。有機体的流出論的発想をもつ。
・主著;『歴史的方法による国家経済学要綱』1843。『16・17世紀のイギリス経済学
史』1851。『国民経済学体系』1854-94年。
(2) カール・クニース(Karl G.A.Knies,1821-1898)
・フライブルク,ハイデルベルクの教授(経済学・統計学)。国民経済を歴史的倫理的
なものと捉えた。諸国民の経済生活の歴史的研究を行い,比較を中心とした機能的方
法によって,国諸国民の経済発展の「発展の類似性」を明らかにしようとした。
・主著;『独立の学としての統計学』1850年。『歴史的方法の立場にたつ政治経済学』
1853年。『貨幣と信用』1873-79年。
B.ロッシャーの経済学方法論(『国家経済学要綱』1843年)。
・方法論の分類──→哲学者の方法(演繹的方法)と歴史家の方法(帰納的方法)
・ロッシャ-の歴史的方法の特徴
(1) 国家経済学は政治的科学である。これは諸国民の経済活動の記述を目指し,この
ため法制史・国家史・文化史をももちいる。
(2) 国民経済を研究するものは,現代の経済関係の観察だけでなく,以前の文化段階の
研究もすべきである。
(3) 多くの現象のなかから本質・法則的なものを取り出す事は難しい。このためには
できる限り多くの諸国民の経済生活を相互に比較する必要がある。
(4) 歴史的方法は軽率に特定の制度を賞賛したり非難したりしない。全ての国民と全
ての文化的発展段階にとって有効ないしは有害な制度というものはない。全ての
制度は,歴史的に相対的なものである。
・のちに,『国民経済の基礎』(1854)において,哲学者の方法を抽象的方法と理想主
義的方法にわけ,前者は経済学の予備工作として必要だとみなした。
・ロッシャーは国民経済学を国民経済の解剖学および生理学ととらえた。そして,自ら
の方法を「生理学的あるいは歴史的方法」と名付けた。諸経済現象の差別性と類似性
に注目し,経済の発展法則と発展段階説を樹立した。
C.クニースの国民経済学観
・『歴史的方法の立場にたつ政治経済学』において,歴史学派の方法論を論ず。
・リストが古典学派に対して「万民主義」だと批判したのにたいして,クニースは古典
学派を「永遠主義」だという。歴史的時間のかなたに理論の妥当性を求める,理論絶
対主義の立場だと批判。
・クニースの国民経済観────
政治経済学は,歴史的発展の所産のひとつであり,それは人類と民族の歴史のある時期の
有機的全体と結びついており,時間,空間,国民性という条件に もとづいて,生成発展
するものである。古典学派の「理論の絶対主義」も,ある時代の産物であるとみた。──
→経済理論の相対性を強調。
3.新歴史学派
A.新歴史学派への展開
(1) グスタフ・シュモラー(Gustav von Schmoller,1839-1917)
・ベルリン大学教授。1870年頃から,社会問題の重要性に注目し,古典学派の自由主義
を批判し,経済学に倫理的価値判断を導入し,社会政策の必要を主張。1872年社会政
策学会を創立。『シュモラー年報』を創刊。国家による中産階級の創設・維持を提唱
・主著;『重商主義の歴史的意義』1884年。『19世紀におけるドイツ小経営の歴史』18
70年。『法および国民経済の基本問題』1875年。
(2) ルヨ・ブレンターノ(Lujo Brentano, 1844-1931)
・ミュンヘン大学教授。労働問題,社会問題に強い関心をもち,シュモラー等とともに
社会政策学会の設立に努力した。自由主義左派を代弁し,労働者の団結権を認め,工
場法や社会立法による労働者保護の必要を主張。講壇社会主義者と呼ばれた。
・「近代資本主義の精神」をめぐって,ウェーバー等と論争。資本主義の精神は無限の
営利欲にほかならず,古代,中世にも存在し,近代になって赤裸々になったとみる。
・主著;『現代労働組合論』2巻,1871-72年。『労働者問題』1882年。『歴史におけ
る経済人』1923年。『イギリスの経済発展の歴史』3巻,1927-29年。
(3) アドルフ・ワグナー(Adolf H.G.Wagner,1835-1917)
・ベルリン大学教授。ドイツ社会政策学会の設立に参加。同学会に参加する講壇社会主
義者のなかでは右派に属した。ビスマルク統治期(1871-1890年)には,その国家主
義的財政・社会政策を擁護した。かれの国家主義的な立場の財政学は,ヨーロッパ各
国の財政政策に大きな影響を与えたという。
・主著;『財政学』4巻,1877-1901年。『一般的理論的経済学あるいは社会経済学』
1901年。
(4) ゲオルク・クナップ(Georg F.Knapp,1842-1926)
・シュトラスブルク大学教授。統計学,農業史,貨幣制度の諸問題を研究。分析的経験
的方法を取る点で新歴史学派に連なる。
・主著;『死亡率の研究』1868年。『貨幣国定説』1905年。
(5) カール・ビュッヒャー(Karl B cher,1847-1930)
・ライプチッヒ大学教授。経済学,統計学,新聞学などを研究講義した。ヨーロッパ経
済史を研究し,独自の発展段階説(家族経済→都市経済→国民経済)を提唱。
・主著;『国民経済の成立』1893年。『労働とリズム』1896年。『経済史論文集』1922
B.シュモラーの経済学方法論とその特徴
・『国家学辞典』(1893年)に掲載された「国民経済,国民経済学,および方法」
・歴史の定義「歴史は諸民族および人間の政治的その他の文化的発展についての全遺産
を蒐集し検討して,一つの理解しうる,それ自体連関のある全体に結合せんとするも
のである」。─→歴史は哲学とともに最も普遍的な科学。歴史と統計学は国民経済学
に観察資料を提供する補助科学。
・歴史を一般史と特殊史とにわけ,経済史・法制史・慣習史などの特殊史が国民経済学
にいかなる効果をあたえるかを考察─→特殊史の成果は歴史的経験的材料を与え,理
論的命題を確証。また,経験的素材から帰納的に経済学上の新しい真理も発見される
・経済史の特殊研究を基礎としてのみ,歴史を国民経済的社会政策的に理解しうる。ま
た,国民経済学の理論を経験的に基礎付けることができるとみた。
・シュモラーの国民経済学は,歴史的倫理学的国民経済学という特徴をもつ。歴史的倫
理学的ということは,自由主義にも社会主義にも対抗する国民全体の立場に立つこと
・シュモラーらの新歴史学派は,経済史研究を行うとともに,社会政策を提唱した。
・シュモラーの歴史的倫理学的国民経済学は,歴史研究と社会政策提案において成果を
挙げたが,理論的研究は不十分になった。また,国民経済学が倫理的科学とされたの
で,理論と政策論との関係が不明確になった。←──ウェーバーの批判。
4.最新歴史学派
A.マックス・ウェーバー(Max Weber,1864-1920)
・エァフルトに生まれ,ハイデルベルクとベルリンの大学で学ぶ。フライブルクおよび
ハイデルベルク大学教授。『社会科学および社会政策雑誌』の編集者。
・主著;
「ロッシャーおよびクニース,ならびに歴史的経済学の論理的諸問題」1903-06年。
「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の『精神』」1904-05年。
「社会科学及び社会政策的認識の客観性」1904年。
『経済と社会』1921年。
『一般社会経済史要論』1924年。
『宗教社会学論集』3巻,1920-21年。
B.マックス・ウェーバーの社会科学方法論
前記の「客観性」論文をはじめとする方法論論文。
(1) 社会科学的認識の客観性
・<文化科学>においては,ある文化現象の意義は,我々の価値理念にそれを関連させ
ることによってあきらかになる。
ある現象を価値理念に関連させる──→その現象の文化的意義を知る。
・認識主体の価値理念──→現象の意義を知るための観点──→重要なものとそうでな
い物との区別が可能になる。
・経験的に与えられたもの(つまり現象)が,価値理念によって調整され,その価値理
念から生じた認識の意味において理解されるうちに,社会科学の認識の客観性がある。
(2) 理念型
・理念型的な概念は,ひとつあるいは若干の観点から,個別的な現象をまとめあげるこ
とによりえられた,ひとつの思想像であり,ユートピアである。
・理念型は,ひとつの純粋に理念的な極限価値であり,経験的事実のうちの特定の意義
ある構成部分をはっきりさせるために,現実をはかる尺度である。
・理念型は,現実の社会現象を科学的に処理するための不可欠の手段である。
(3) 没評価性論
・理念型そのものによっては価値判断する事はできない。 他方,価値判断しないことに
よって理念型をつくることができる。
・社会現象についての認識は,価値判断をせずに,没評価的になされるべきである。
・また,社会科学的認識の結果について語るときにも,没評価的になされるべきだ。
・政策的領域で社会科学(経験科学)が示すことのできるものは,取らざるをえない手
段,それを取った場合に避けることのできない付随的結果,および,それぞれの手段
の実践的帰結の評価をめぐる対立の発生などである。
・社会科学は,実践家にたいして,実践的問題について考える際の<究極の>態度の種
類,それらのなかから何れかを選ぶ際に考慮すべき事実(政策選択のもたらす結果等
)などを,告げることができるだけである。
C.マックス・ウェーバーの資本主義観と近代資本主義成立論
(1) 唯物史観にたいする批判
・唯物史観をひとつの理念型と捉えることにより,それを相対化した。それは,歴史を
説明するひとつのモデルと見た。
・経済事情に歴史発展の説明をもとめる唯物史観にたいして,近代の人間のエートスと
いう精神的なものに,近代資本主義成立の原因をもとめる,別の理念型を提唱した。
・これが論文「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の『精神』」。その内容は?
(2) 問題提起
・近代企業の資本家や企業家また熟練労働者にはプロテスタントが多いという事実。
・プロテスタントは,支配層も被支配層も,経済的合理主義への愛着を示してきた。
・プロテスタントに見られる非現世的禁欲的信仰熱心と資本主義的営利生活に携わる事
の間に内的親和関係がある。
・資本主義は,古今東西に存在するが,近代資本主義は西ヨーロッパとアメリカに見ら
れる。この近代資本主義は,独自のエートスを持っている点で,それ以前の資本主義
と異なる。また,近代資本主義は,合理的経営による資本増殖と合理的な資本主義的
労働組織を伴う点で,それ以前の資本主義と異なる。
・近代の「資本主義の精神」とは何か。──→自分の資本を増加させることを自己目的
と考えることが各人の義務だという思想。これは倫理的な色彩を持つ生活の原則(エ
ートス)という性格をおびている。
cf.フランクリンの徳目(時は金なり。信用は金なり。貨幣は繁殖し子を生むものだ。
時間を守り法に違わぬこと。信用の重要さ)
・近代資本主義の精神の中にみられる職業義務という観念。──→労働力や物的財産
(「資本」)を用いた単なる利潤追求の営みにすぎないにもかかわらず,各人は自分
の「職業」活動の内容を義務と意識すべきだと考え,また事実意識している。
・
近代資本主義の精神──→正当な利潤を天職(Beruf)として組織的かつ合理的に追求
するという心情。近代資本主義的企業は,この心情と適合的である。
・ では,こうした資本主義精神は,どのようにして成立したのか。とりわけ,宗教的要
因との関係はどうか。こう問題提起して,ウェーバーはピュ-リタニズムのエートスが,
近代資本主義の精神を生じさせたと答える。
「・・・ある宗教の倫理教説ではなく倫理的な態度・・・これこそ,社会学的な意味
での,<その宗教に>独特の<エートス>なのである・・・・・。ピューリタンの場
合,この倫理的態度とは,生活実践の特定の方法的・合理的な在り方にほかならなか
ったのであり,この生活態度こそ───所与の条件の下で───資本主義の<精神>に道
を開いたものであった。」(『プロテスタンティズムの諸教派と資本主義の精神』より)。
・「キリスト教的禁欲精神」→「天職理念を土台とした合理的生活態度」。
(3) 禁欲的プロテスタンティズムの天職倫理
A.カルヴィニズム──→「恩恵による選びの教説」(予定説=人々の救済は神によって予め
決定 されており,人間の善行によっては変更できないものであるという教理)。カルヴ
ァン派信徒は,自分で自分の救いの確信をつくり出すのであり,組織的な自己審査によっ
てつくり出す。いまや,かれらは,世俗的な職業生活の内部で,禁欲の理想を追求しなけ
ればならなくなった。こうして,倫理的な生活態度の組織化が,行われるようになった。
B.敬虔派(パイエティズム)
・「敬虔派が育成した諸徳性は,むしろ,一方では『職業に忠実な』役人,雇人,労働
者,家内生産者たちが,他方では,主として家父長的精神の雇い主が,神の嘉(よ
み)したまう砕かれた心という形で表しえたような類のものであった。カルヴァン派
は,これに比して,市民的・資本主義的な企業家の厳格,実直,行動的な心情に一層
多くの親和性をもっていたように思われる。」(『精神』より)。
C.メソジスト派(方法派)
・「感情的でしかも禁欲的な宗教意識と,カルヴァン派的禁欲の教理的基礎への無関心
の増大ないしはそれの排斥との結合という特質を示すのは,大陸における敬虔派のイ
ギリス=アメリカにおける対応物ともいうべきメソジスト派である。」その名称は,
救いの確かさを獲得するための生活の「方法的」組織化という事実を示している。
D.洗礼派運動から生じた諸セクト(バプティスト派,メノナイト派,クエーカー派)
・「洗礼派系の諸教派は,予定説の信奉者,わけても厳格なカルヴァン派と並んで,救
いの手段としての一切の聖礼典を根本から完全に無価値なものとし,こうした宗教に
よる現世の『呪術からの開放』を徹底的に成しとげたのであった。・・・・救いは功
績によってかちとりうるものではなく,神の恩恵の賜物なのだが,しかし,良心にし
たがって生活する者だけが,自分を再生者と考えてもよいというのだった。」
(4) 禁欲と資本主義精神から近代資本主義の成立へ。
・ カルヴァン派から発生したイギリスのピュウリタニズムの代表的信徒としてのリチャ
ード・バクスターの見解。「バクスターの主著には,肉体的にせよ,精神的にせよ,
厳しく絶え間ない労働への教えが繰り返し,時には激情的なまでに,一貫して説かれ
ている。」「労働意欲がないことは恩恵の地位を喪失した徴候なのだ。」「労働その
ものではなくて,合理的な職業労働こそが,まさしく神の求めたまうものなのだ。」
・カルヴィニズムの世俗内禁欲のエートス──→近代資本主義の精神──→近代資本主
義の成立。「プロテスタンティズムの世俗内禁欲は,所有物の無頓着な享楽に全力を
あげて反対し,消費を,とりわけ奢侈的な消費を圧殺した。その反面,この禁欲は,
心理的効果として財の獲得を伝統主義的倫理の障害から解き放った。利潤の追求
を合法化したばかりでなく,それを神の意志に添うものと考えて,そうした伝統主義
の軛を破砕してしまったのである。」
・資本主義の機構の成立後は,職業義務をもった人間類型が再生産される。
(5) 近代資本主義の機構とその前提
・近代資本主義の一般的な前提は合理的資本計算が行われることであり,その前提は,
すべての物的獲得手段が私有財産として営利企業によって占有されていること,市場
の自由,合理的な機械化された技術,合理的な計算可能な法律,自由な労働,経済の
商業化などであった。
・近代資本主義を成立させたものは,ひとつには,上記のような合理的な永続的企業,
合理的簿記,合理的技術,合理的法律などであるが,それに加えて,合理的心術(ゲ
ジヌンク),生活態度の合理化,合理的な経済的エートスが不可欠である。(『経済
史・一般社会経済史要論──講義遺稿』)
第 三 部 社 会 主 義 の 経 済 思 想
Ⅰ.初期社会主義の経済思想
(1)初期社会主義の諸相
A.社会主義思想の先駆者たち
トマス・モア(Thomas More,1478-1535) 『ユートピア』(Utopia,1516),
ウィンスタンリ( イギリスのピュリータン革命の急進左派),
モレリとバブーフ( フランス),
ゴドウィン(William Godwin,1756-1836)『政治的正義』
(An Enquiry concerning Poli
tical Justice,1793)
B.初期社会主義の成立の背景とその諸潮流
産業革命後の労働者の悲惨な労働状態( 原生的労働関係)
や, 資本主義の生産力によっ
て小生産者が没落するという状況を背景に, 私有財産制度にたいする批判論として,
初
期社会主義は成立.
C.空想的社会主義( サン・シモン,
フーリェ, オウエンなど)
資本主義の開発した生産力を高く評価し, これを社会問題の解決に利用しようとする.
→ 支配者の善意や理性に期待.
有産者の財政的援助に期待.
E.リカード派社会主義( ホジスキン,
トムスン, ブレイ)
全労働収益権( 「労働の全生産物はその生産者に保障されなければならない」トムスン
)
労働貨幣論( 金本位制にかわる労働本位制→労働貨幣は需要不足を解決し,
失業の解消
に役立つ)
協同組合村( 人間は環境の産物なので,
環境を改善することにより人間を改良しうると
みる→オウエンの理想村,
ニュー・ハーモニー村, 「オウエン氏の平行四辺形」)
トムスン( 協同組合村をつくる資金は労働組合の蓄積資金による)
フランシス・ブレイ( 資本の有償国有化方式の提唱→労働量とスターリングの両方の表
示をもつ紙幣をつくり, これで資本家から固定資本を買収する)
F.革命的社会主義
バブーフ( Gracchus Babeuf,1760-97,土地共有による農地法を要求.
平等党を組織し,
人民の蜂起により革命政府 を樹立し, 平等な社会をつくろうとしたが,失敗し処刑さ
れた).
ブランキ( Louis Auguste Blanqui,1805-81.バブーフ主義を継承.
労働者の武装蜂起に
よる共産社会の実現を要求し, 蜂起に参加したため,生涯の多くの期間を牢獄でおくっ
た。)
G.プルードン(Pierre Joseph Proudhon,1809-65)
フランスの無政府主義の創始者. 主著『経済的諸矛盾の体系,
別名, 貧困の哲学』 (1
846). 『労働者階級の政治的能力について』(1865)のなかで,経済上の「相互主義」と
政治上の「連合主義」を特徴とした組織論を提唱した. また,地域主義の先駆者.
(2)マルクス学派の形成と展開
A.マルクス主義の成立と発展の社会的背景
ドイツの1848年革命期に,ブルジョワ革命の限界を批判するプロレタリア社会主義革命
論として, マルクス主義は形成されはじめる→その後,
イギリス古典学派の経済学を批
判的に摂取し, マルクスの経済学説は成立した。その社会的背景としては,産業資本主
義のもとでの労働者の劣悪な労働条件と私有財産に由来する社会的不平等などの社会問
題があった。
B.いわゆるマルクス主義の三つの源泉
当時の最高の学問的成果であった,ヘーゲル哲学, 古典経済学,
フランス社会主義思想
などを批判的に吸収して, 唯物史観と唯物弁証法に立脚したマルクスの経済思想が成立
した.
C.マルクス主義とマルクス経済学の関係
いずれの経済学説も固有の歴史観や思想をもつ.マルクス経済学も唯物史観と唯物弁証
法という方法論をもつ.これらはプロレタリアート( 労働者階級)
の世界観と関連した
イデオロギーである. これにたいして,マルクス経済学は,そうした歴史観や方法論に
基づきながらも, その理論内容は古典学派の理論に対する批判にもとづく科学的なもの
であった→ 唯物史観・唯物弁証法というイデオロギーと経済理論は,いちおう区別さ
れるべきものである( 後者は科学としての性格をもっている)
。
D.マルクスの経済理論の特徴
投下労働価値説に基づいている. 資本蓄積論を重視している.
資本の生産過程( 『資本
論』第一巻,)に基づき資本の流通過程(
第二巻) を説き,さらに, 剰余価値の分配に関
する資本の総過程( 第三巻)
を説くという構成になっている( ケネー,スミス, リカー
ドゥなどの古典経済学の伝統を踏まえ, これらを批判的に継承している).
E.マルクス学派の展開
修正主義論争→帝国主義現象の出現による資本主義崩壊論などの正統派マルクス主義の
ドクマをめぐる論争.(カウツキー対ベルンシュタインの論争,1898-1903年)
帝国主義論争→通商政策論争(1898-1902年),植民地政策論争(1904-1907年)
など
F.独占資本主義論と帝国主義論の類型
資本蓄積論的な帝国主義論・・・ヒルファディング, レーニン
世界市場論的な帝国主義論・・・パルヴス, ルクセンブルク
両者の折衷論または総合の試み・・・カウツキー, ブハーリン
G.マルクス経済学の流れにたつ現代資本主義論
国家独占資本主義論,
組織資本主義論,
レギュラシオン理論,
Ⅱ.初期マルクスの経済思想
(1)初期マルクスの生涯と活動
1818・5 ドイツのトリーア(プロイセン邦,
西南ドイツ)に生まれる
1835 ボン大学へ入学
1836 ベルリン大学へ入学. 青年ヘーゲル派と交流
1839-40 ( 学位論文)
1842 『ライン新聞』のための諸論説. 『ライン新聞』編集者としてケルンに移る
1843 ( ヘーゲル法哲学批判).「ユダヤ人問題について」
1844 「ヘーゲル法哲学批判序説」.(経済学・哲学草稿).『聖家族』.
エンゲルス
と知り合う.
1845 「フォイエルバッハに関するテーゼ」. ブリュッセルに移る.
1846 ( ドイツ・イデオロギー).(
アンネンコフへの手紙).ヴァイトリングと対立
1847 『哲学の貧困』. 共産主義者同盟に加入
1848 『共産党宣言』. 『新ライン新聞』のために約80編の論文.
パリついでケル
ンに移り, 『新ライン新聞』の編集者になる.
フランス, ドイツ中心に48年
革命が勃発.
1849 『賃労働と資本』. 『新ライン新聞』のために約20編の論文.
革命の敗北に
よりパリをへてロンドンへ亡命する.
1867 『資本論』第一巻, 第一部「資本の生産過程」初版(
ハンブルク. オットー
・マイスナー書店.1000 部)
1883 死亡.
1885 『資本論』第二巻, 第二部「資本の流通過程」刊行(
ハンブルク, オットー
・マイスナー書店)
1894 『資本論』第三巻, 第三部「資本主義的生産の総過程」刊行.
(2)初期のマルクスの社会・経済思想
(1)マルクスは, 『ライン新聞』編集者として,
社会活動を始めたころには,ヘーゲル
左派の立場から, 封建的で専制的なドイツ社会の民主主義革命をめざし,ヘーゲル『法哲
学』における自由を実現した倫理的実体としての国家という観点から,プロイセン政府の
出してくる言論統制などの反動的立法を批判していた。しかし,森林盗伐法の批判をおこ
ない,初期の社会主義・共産主義の思想と直面するなかで,改めてヘーゲル哲学, 古典経
済学, および初期社会主義を検討し,
自己の思想を形成する必要を痛感するにいたった。
(2)その最初の成果が『経済学・哲学草稿』(1844)であった。同書の「疎外された労
働」論は, かれの資本主義社会への最初の理論的批判であった。そこではかれは,自由で
目的意識的生産活動をおこなうことが人間の類的本質であるという人間観から,私有財産
制度の支配する資本主義社会においては,賃労働者の労働が疎外された労働に転化してい
るところにこの社会の問題があるとみなした。そして,疎外された労働をば, 労働者から
の労働生産物が疎外されていること, 労働が労働者にとって外的で疎外されたものになっ
ていること,賃労働者にとって労働はかれの個人的生活のための手段になっているのでか
れからは人間の類的本質が疎外されていること, 人間と人間との対立が生じていることな
ど,四つの側面から規定したのである。このようにこの段階では, マルクスは啓蒙主義の
自然法思想のように,人間の自然についての見解にもとづき, 現実社会の人間の置かれた
状態を批判するという仕方で,資本主義社会を批判したのである。したがって,そこでは
近代啓蒙思想( ブルジョワ思想)
とよく似た思想構造にたって,現実の人間労働や社会制
度を批判しているのである。
(3)しかし,しばしばマルクス主義は,経済史観ととらえられ,政治や社会の諸現象・
諸問題を経済過程から解釈し説明するものとされてきたため,マルクス主義の人間観と
いった問題は論じられることが少なかった。1930年頃以後,
ゲオルク・ルカーチ( ハンガ
リー人),ヘルベルト・マルクーゼ(
ドイツ人) アンリ・ルフェーブル( フランス人),梯明
秀や梅本克己などの哲学者たちが, 『経済学・哲学草稿』における初期マルクスの人間観
・労働観に注目し, これと後期の思想とを結びつけてマルクス主義を解釈するようになっ
たのは,ひとつにはそのせいであるとおもわれる。それともうひとつの理由は,ロシア・
マルクス主義の変種としてのスターリン主義の客観主義的な唯物史観解釈を批判するため
に,初期マルクスの人間観にたちかえる必要があったためであろう。1930年代には,
ス
ターリン主義の誤りは, いくつかの点であらわれはじめていたのである。
(4)しかし『経済学・哲学草稿』執筆以後,マルクスはエンゲルスの影響もあって,
モーゼス・ヘスなどのヘーゲル左派の思想を検討し,また経済史や古典派経済学などを研
究して,自己の社会観・歴史観を形成しようと努力した。その成果が『ドイツ・イデオロ
ギー』(1846)であった。これもまた,1926
年にリャザーノフの手によりその第一章が発表
されるまで世に知られなかったものである。しかし,マルクスやエンゲルスの唯物史観を
とらえるには,唯物史観の公式を述べた『経済学批判, 序言』(1859)だけでは不十分であ
り,この『ドイツ・イデオロギー』やのちの『経済学批判要綱』(1857-59) などをも参照
し, その形成過程をみなければならない。
(5)『ドイツ・イデオロギー』(1846)は,ルートヴッヒ・フォイエルバッハと,
モーゼ
ス・ヘスなどのヘーゲル左派の社会観・歴史観を批判しつつ,自己の見解を述べたもので
ある。とりわけ第一章のフォイエルバッハ批判の部分が重要である。マルクスたちは,歴
史観の前提を現実の人間の物質的生活条件, したがって諸個人の生産と交通形態におき,
そこから歴史記述をおこなうべきだと考えた。そして,諸民族の発展段階を,部族的,古
代的,および封建的な所有形態の発展としてとらえた。さらに,それ以後については,物
質的労働と精神的労働との分業,とりわけ都市と農村との分業の展開ととらえ,中世いら
い同職組合,マニュファクチュア,大工業の順序で分業が発展してきたとみたのである。
そして,最後の大工業の時期において生産諸力と交通形態との間の矛盾が爆発して革命と
なり,諸個人の真の結合をもたらす真の共同社会が成立するとみなした。この真の共同社
会に比べると,ブルジョワ国家における諸個人の共同性は幻想の共同性にすぎないとみる
のである。
(6) また『ドイツ・イデオロギー』における唯物史観によると,社会全体( 社会構成
体) はいくつかの層をなしており,基礎的な層として経済過程(
市民社会) があり,これ
は生産諸力と交通形態との統一ととらえられる。この土台のうえに,国家制度, 法・政治
制度などの諸制度があり,さらにそのうえに, 理論,
哲学, 宗教, 芸術,
文化などの社会
的意識形態がそびえたつ。これらはのちに上部構造と呼ばれるにいたる。そして,人間の
社会的意識がかれの社会的存在によって規定されているように,社会構成体の上部構造は
その土台によって決定されるとみていた。もっとも,このことは意識が存在に反作用する
ように,上部構造もまた土台に反作用するということを否定するものではなかった。マル
クスが歴史発展の原動力とみなす階級闘争は, 市民社会(
土台) における生産力と交通形
態との矛盾によって, 生み出され,
制約されていると見做されていたのである。
Ⅳ.第二インターナショナルおよび社会民主党内の修正主義論争
(1898-1903)
1. 修正主義論争におけるベルンシュタインの問題提起
A.問題の所在───修正主義論争研究の目的と意義
・第2インターの資本主義崩壊をめぐる論争から,帝国主義の新現象の研究が始まっ
た。 ・資本主義崩壊論の是非が,社会運動の在り方を決定する。
・マルクス主義の諸理論部分(唯物史観,弁証法,労働価値論,資本主義崩壊論,革命
と改良の関係,議会活動の評価,国家の経済・社会への干渉)をめぐる論争。
・ベルンシュタイン修正主義論は,現代社会民主主義の源流のひとつ。
B.修正主義論争の社会的背景
・競争的資本主義は大不況をへて独占資本主義へ──→資本主義崩壊論をめぐる論争.
・崩壊待機の立場への批判──→積極的な改良活動の主張.
・19世紀末以来,労働組合の活動の活発化や,地方自治体での社会民主主義者の活動
の活発化──→社会改良活動の見直し始まる.
・ドイツ社会民主党の受け入れたマルクス主義(晩年のエンゲルスの見解=議会と選挙
を重視)の影響.
・修正主義論争の発生した原因──→ドイツ社会民主党の理論(崩壊と革命)と実践
(改良的活動)との矛盾.
C.ドイツ社会民主党の「エルフルト綱領」(1891)───修正主義論争の前提
この綱領の資本主義観は,『資本論』第1巻第7篇に述べられた資本制的蓄積の一般的
法則をより極端な形で解釈したものである。それによると,資本主義発展は,集中法則
の作用による中間階級の両極分解と階級対立の激化,および資本主義の無政府性と大衆
の消費力の制限に由来する恐慌の激化をもたらし,この結果,いずれは資本主義は崩壊
し,社会主義に必然的に移行するとみる。
第一部 資本主義発展の見通し (カウツキー執筆)
資本主義発展=崩壊像
・小経営の没落──→プロレタリア化,生産手段の少数の資本家と地主への集中
・人間労働の生産力の成長──→ブルジョワジーの富の増加。プロレタリアートと没落
中間層の生存の不安定性,貧困,圧迫,奴隷化,搾取の増大。
・プロレタリアートとブルジョワジーとの階級闘争の先鋭化。
・生産の増大に比べての大衆の消費の制限により,恐慌は広範囲で破壊的になる。
・生産手段の私的所有は,資本主義のもとでは搾取の手段になった──→社会のための
社会によって営まれる社会主義的生産への変革のみが,最高の福祉をもたらす。
・この社会的変革は,プロレタリアートの解放だけでなく,人類の解放を意味する。こ
の変革は,労働者階級の仕事である。
・階級闘争は,政治闘争であり,労働者階級は政治権力を獲得することなしには,生産
手段の総体的所有へ移行できない。
・他のすべての国の労働者階級との連帯
・階級差別だけでなく,あらゆる種類の搾取と抑圧と闘う。
第二部 当面の要求 (ベルンシュタイン執筆)
○一般的な要求
・20才以上の国民の秘密投票による,普通・平等・直接選挙と投票権.
・人民による直接選挙.
・民兵制の採用.
・言論,結社,集会の自由.
・男性に比べて婦人を不利とする全ての法律の廃止.
・宗教の私事たることの宣言.
・学校の非宗教性(の保持).
・訴訟と弁護士の無償制.
・医療,薬剤投与の無償制,死者埋葬の無償制.
・累進的な所得税および財産税.
○ 労働者階級のための要求.
・効果的な国民的および国際的な労働者保護立法.
a. 最高8時間の標準労働日の確定.
b. 14才以下の児童にたいする職業労働の.禁止
c. 夜間労働の禁止.
d. 毎週最低36時間の連続した労働の休止.
e. 現物給与制度の.廃止
・全ての営利企業に対する監視。
・農業労働者と工業労働者とを法的に同等視すること.
・団結権の確保.
・国家による前労働者保護の引受.
D.ベルンシュタインの問題提起
・ベルンシュタインの生涯と活動.
・連続論文「社会主義の諸問題」(『ノイエ・ツァイト』誌,15巻-1・2号,16巻-2
号)において,社会民主党の資本主義崩壊論と静観主義を批判.
(1) 社会改良活動の重要性を強調
論文「社会民主主義の闘争と社会の革命」──→資本主義社会のなかで社会主義的
な意味をもつ改良を積み重ねるという立場を強調。
(2) 資本主義崩壊論を否定し,最終目的でなく運動を強調
論文「崩壊論と植民地政策」──→崩壊論の論拠は,経済の集中の進展により階級対
立が激化し,また経済恐慌が深刻化すること。両者を批判し,社会主義という最終目
的よりも,運動を強調。労働者階級の政治教育と国家の民主主義化の必要性を強調。
「わたしは,ひとびとが概して『社会主義の最終目標』のもとに理解しているものに
ついて,ほとんどまったく理解できないし,関心も持っていない。この目的は,どん
なものであれ,わたしにとって無であり,運動がすべてである。そして,運動のもと
で私が理解しているのは,社会の一般的運動つまり社会進歩であるだけでなく,この
進歩を実現するための,政治的および経済的なアジテーションと組織化なのである」
(前掲論文,556頁)。
(3) 最終目的をめぐる議論
・最終目的への無関心を非難されたので,論文「批判的な間奏曲」のなかで,「協同性
の全面的な貫徹」を,社会主義の一般的目的と主張。生産手段の社会化も,この一般
的目的の手段にすぎないと見た。最終目的よりもここの時点での個別的な目的の実現
に努力すべきだとしたのである。
2.左派理論家たちのベルンシュタイン批判
A.修正主義論争の経緯
・1892年6月29日の社会主義者ミルラン(A.E.Millerand,1859-1943)が,急進共和
主義のワルデック・ルソー内閣への入閣の是非をめぐる論争──→フランス社会主義
者の分裂(革命派と改良)派
・ハノーヴァー党大会におけるベルンシュタインをめぐる論争(エアフルト綱領の書か
れていない部分をめぐる論争───社会制度の改革は議会主義的な行動によるべきか
革命的な行動によるべきかという問題)
・フォルマール(G.v.Vollmar,1850-1922)による改良主義の提唱─→南ドイツの小農民
層にたいする積極的な保護を主張。
・1898-1903年にかけて,修正主義・改良主義派(ベルンシュタイン,フォルマール,
ダーフィット)と党中央派(カウツキー,ベーベル)左派(パルヴス,ルクセンブル
ク)との間で論争.第2インター内でも論争。
・1903年8月ドイツ社会民主党ドレスデン党大会において,修正主義否認の決議。
・1904年8月の第2インターナショナルのアムステルダム大会でも同様の決議.
B.パルヴスのベルンシュタイン批判
・連続論文「ベルンシュタインによる社会主義の転覆」(『ザクセン労働者新聞』
1898.1.28-3.6)───ベルンシュタイン批判の最初のもの。資本主義崩壊論と待機主
義に陥らず,ベルンシュタインの改良主義・漸進主義を批判し,プロレタリアートによ
る政治権力の奪取を主張した。
・工業,農業,商業・運輸業等における集中法則の貫徹について検討→工業,商業・運
輸業等では集中は進展。
・工業資本家と工業プロレタリアート階級との勢力の計算(163.6万人対1796万人)─→
社会階層の編成の点からは社会革命の客観的条件はある。
・社会主義実現の前提条件─→生産の高度の発展・社会の解体の進展・プロレタリアー
トによる政治権力獲得の条件の成熟。
・社会革命の主体的条件を重視する理論。
・生産の社会化と政治組織の民主化とを結合するという視角をとる。
・社会革命政府の課題(過渡的な政策を示した。)───賃上げ,労働時間・労働条件
の法的規制,家賃の切り下げ,不動産抵当の除去,政治組織の民主主義的改革,地方
自治体の行政の拡大,生産の社会的組織の形成と労働力の目的意識的な配分。
C.ルクセンブルクのベルンシュタイン批判
・ルクセンブルク(Rosa Luxemburg,1871-1919)の生涯
〇『社会改良か革命家』(1899)におけるベルンシュタイン資本主義観の批判。
・信用制度の発達と企業家連合(カルテル,トラスト)の発達による資本主義の(危機
への)適応能力の増大という論点に対する批判。それらによっても,資本主義の無政
府性は克服されず,資本主義崩壊は不可避とみた。
〇論文「ベルンシュタインにたいするカウツキーの論駁書」
・彼女は,エアフルト綱領にたいするベルンシュタインの批判を,有産者は減少せず増
大すること,小経営は減少しないこと,広汎で破壊的な恐慌勃発の蓋然性は少なくな
ること等,三点にまとめ,反論した。
・彼女は世界市場での全般的な過剰生産による恐慌は阻止できないと主張した。
〇『社会改良か革命か』における彼女の社会運動論
・社会改良による社会主義の漸次的な導入という構想に反論。
・労働組合の活動は社会主義とは関係がないと批判。
・国家の立法による社会改良は,(資本主義のもとでの)国家が階級国家なので,社会
主義的なものとは言えないと批判。
・プロレタリアートの政治権力の獲得が問題だと批判。
〇『社会改良か革命か』の第二部におけるベルンシュタイン批判
・株式会社制度と協同組合にたいするベルンシュタインの高い評価に反論。
〇ルクセンブルクのベルンシュタイン批判の特徴。
経済理論的には,資本主義の適応能力論を批判し,社会主義の歴史的必然性を主張。
社会思想的には,社会改良主義を批判し,労働者の政治権力獲得による社会主義革命
を主張した。
D.カウツキーの修正主義批判。
〇カウツキー(Karl Kautsky,1854-1938)の生涯と著作
・ドイツ社会民主党の代表的理論家。エァフルト綱領第一部の執筆者。SPDの理論機
関誌『ノイエ・ツァイト』誌の編集者。
・主要著作;
『ベルンシュタインと社会民主党綱領』(1898)。
『通商政策と社会民主主義』(1901)。
『社会革命論』(1902)。
『社会主義と植民地政策』(1907)。
『権力への道』(1909)。
〇『ベルンシュタインと社会民主党綱領』におけるベルンシュタイン批判の特徴
『エァフルト綱領』第一部の資本主義崩壊論の擁護に終始した。
〇 1900-1910年の間の帝国主義の先駆的な研究の特徴
前記の諸著作により,帝国主義についての先駆的な研究を行った。かれの見解は,
世界市場論的な帝国主義論と資本蓄積論的な帝国主義論との折衷論であったが,ヒ
ルファディングやV.I.レーニンにも影響を及ぼした。但し,第一次大戦中の超帝国主
義論にたいしては,レーニンによる厳しい批判がなされた。