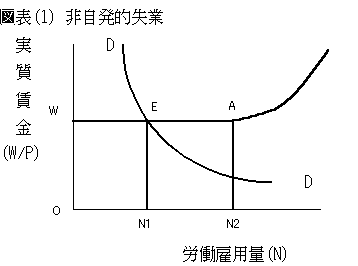
「近代経済学史」(昼間部,秋学期)
「経済学史Ⅱ」(夜間部)
第一部
マルクス経済学の展開
[I]
第一次大戦前のドイツ社会民主党および第二インターナショナルの 帝国主義論争と帝国主義論の諸類型
(1)通商政策論争と帝国主義認識の端緒
(1)ドイツ帝国の通商政策と社会民主党内の通商政策論争
(A)
ドイツ帝国の通商政策の推移と1902年の新関税法
(1) 1902年までのドイツの通商政策の推移
・世界的な自由貿易の時代(1860
年代-1873
年ころまで)
・1879-80年の関税法(「穀物と鉄の関税」宰相ビスマルク)
・宰相カプリヴィーの「新航路」路線→自由貿易を志向(農業関税率を下げ,工業製品
の輸出市場拡大を目指した)
・宰相ホーエンローエの結集政策(重工業家とユンカー階級の利害の調整)
(2) 1902新関税法の内容とその意義
・1901年7 月26日の『帝国官報』に発表された新関税法(
小麦トン当たり最低55マルク
, 一般65マルク, 最高75マルク,
またライ麦・
カラス麦最低50マルク, 一般60マルク
, 最高75マルクの関税率を中心とするもの)。
・新関税法の特徴→工業原料や補助材料の輸入にたいしては,
関税の廃止・ 軽減・
据え
置きをおこなうが,主要穀物にたいしては最高および最低関税率をもって手厚く保護
していること。→
重工業家とユンカー階級の階級同盟
(B) ドイツ社会民主党内の通商政策論争の展開
(1) 社会民主党の通商政策にたいする態度の変化
・第一次大戦まえには,SPD
は,
農業関税や財政関税には一貫して反対したが,
工業関
税に対する態度は時代につれて変化した→
育成関税論から自由貿易へ。
(2) 第一期(1863-1879年) --工業育成関税論と便宜主義的立場--
・消費財への関税には反対したが,工業関税は,リストに従って,賛成した。(ブラッケ)。
・個々の関税にたいして,
その都度, 賛否いずれかを決めるという便宜主義的な立場。
(3) 第二期(1879-1897年) --自由貿易主義の立場の明確化 --
・エンゲルスの論文「
保護関税と自由貿易」(1888)
→保護関税は発展の障害になってお
り,
自由貿易だけがこれ以上の進歩をもたらしうると主張。
(4) 第三期(1898-1914)
--1898年のシュツットガルト党大会での通商政策論争と自由貿
易主義の確立。--
・シッペルなどの修正派は,食料関税は廃止されるべきであるが,工業関税は黙認する
という立場をとった。これに対して,
カウツキーは,
ドイツ工業が関税保護を必要と
しない程度にまで発展していると評価する。
工業, 農業を問わず完全な自由貿易要求
(5) シュツットガルト党大会(1898
年)
以後の通商政策論争
・SPDは,公式には全党一致してすべての保護関税に反対するという態度をとる。
(2) 通商政策論争の争点(資本主義観,方法論をめぐって)
(A) カルヴァーの通商政策論
・小冊子,Arbeitsmarkt
und Handelsvertr ge,Frankfurt a.M.,1901
カルヴァーは,労働者の経済的利益という基準と,そのためには,
一国内での大経営
の発展が不可欠だとする国民経済的な観点より,
工業保護関税に寛容な姿勢をみせた
・ドイツの工業製品の輸出を増大させるために,中欧諸国とは関税同盟に連なるような
関税協定の締結,英・露・米とは互恵主義的な関税協定の締結を目指した。
(B) シッペルの通商政策論
(1) シッペルやカルヴァーの工業関税容認論
・かれらの保護関税容認論の論拠→保護主義的な政策を社会主義的なものとみる見解。
労働者の生産者としての利害から,特定の工業の保護関税を認めるべきだとする見解
・その根底にある根本的見解→国民経済という枠組みにたつ見方,生産力の発展という
観点から独占的資本組織の発展をも社会主義への移行の一因だとみる生産力的主義主
義的な見方。
(2) 『通商政策綱要』(1901)に見られるシッペルの通商政策論
・Max
Schippel, Grundz ge der Handelspolitik, Berlin 1902 .
イギリスとドツの通商政策の変遷をその社会的背景と関連させて叙述。
・シッペルは,ドイツのような後進国では工業を発展させるために,関税保護が必要だ
と考えていた。保護関税によって外国の強力な競争者を排除することは,ドイツ工業
の振興に役立ち,ひいては労働者階級の生活状態の改善をもたらす。→「農業関税の
過度の引き上げ」に反対,労働者と企業家との貿易政策上の同盟を擁護。
(3) シッペルのドイツ資本主義観
・ドイツ資本主義を工業発展という線上で捉え,イギリスと比較する。→これでは,1
9世紀末以来のドイツ資本主義の段階的・構造的変化の認識は不可能と言える。
・保護関税を労働者の直接的な利害から評価するという方法→全体としての保護関税が
資本・ 賃労働の階級関係におよぼす客観的な作用は捉えられないと言える。
(C) 『通商政策と社会民主主義』(1901)におけるカウツキーの通商政策観
(1) カウツキーの通商政策観
・小冊子,Karl
Kautsky, Handelspolitik und Sozialdemokratie, Berlin 1901.
ビスマルクの「 穀物と鉄」
の保護関税が出されてきた根拠が論じられている。→複数
の工業国の成立により,自由貿易から保護関税へ移行→
これを競争的資本主義から
独占資本主義への移行と関連させて把握した。
・新関税法の特徴とSPD
の採るべき通商政策 ・世界戦争への傾向-帝国主義論の先駆
(2) カウツキーのシッペルにたいする反論
・新関税法譓賰重工業家とユンカー階級との結集政策を意味し,軍備強化の財源となる
・すべての保護関税に反対し,自由貿易の実現を要求するという原則。
(3) カウツキーのドイツ資本主義観
・ドイツ工業は,関税保護を必要としない程度まで発達しているとみる。
・通商政策が社会関係の発展に及ぼす客観的な効果を解明しそれへの態度を決定する。
(4) 論争の結末
・1898年以後, 完全な自由貿易が主張されるようになったが,
保護関税の歴史的性格の
変化が明確に認識されたのではなかった。
→関税問題から帝国主義の解明への模索。
(3)通商政策論争における帝国主義認識の端緒
(A) ヒルファデイングの経済学への関心
・ヒルファデイングの経済学研究の開始
→『ボェーム=
バウェルクのマルクス批判』
(1904),かれの1902年から1905年ころまでの問題意識は,価値論研究,
通商政策論研究
,ゼネスト問題研究など。
(B) 「 保護関税の機能変化」
におけるヒルファデイングの通商政策論
・
Rudolf Hilferding, Der Funktionswechsel des Schutzzolles. Tendenz der moder
nen Hanelspolitik. in; Neue Zeit, XX-2,1903.
・1903年の通商政策とそれ以前の通商政策との相違点譓→保護関税の機能変化(
育成関
税からカルテル保護関税へ,
防御手段から略奪手段へ)
・通商政策の変化の背景にある資本主義の変化→独占資本主義,世界政策(帝国主義)
(C) ヒルファデイングの通商政策論の特徴---帝国主義認識の端緒---
・カウツキーの通商政策論→帝国主義論の萌芽と帝国主義への自由貿易主義的批判。
・ヒルファデイングの通商政策論の特徴→段階認識の発生,帝国主義を捉える視角。
(2)
植民地政策論争と帝国主義認識の深化
(1) 第一次大戦までのドイツの植民地政策の展開
(A) ドイツの植民地政策展開の諸段階
・第一期(1848-1879)
譓賰移住植民地が重視された。
・第二期(1879-1890)
譓賰工業製品の販路と原料供給地としての植民地の獲得と経営。
・第三期(1890-1906)
譓賰ドイツ社会の内部対立の激化により移民が増大。
・第四期(1907-1914)
譓賰デルンブルクによる合理的な植民地経営。'10年以後中東進出
(B) ドイツの植民地の特徴と経済的効果
・ドイツ領南西アフリカ譓賰グアノの輸出。銅,ダイヤモンドの産出。農園拡大。
・ドイツ領西アフリカ(トーゴー,カメルーン)譓賰象牙,ゴム,コプラ,椰子油,穀物の輸出。
・中国におけるドイツ植民地(
Kiautschou, 青島)
譓賰生糸, 皮革,
などの輸出。
・ドイツの植民地の効果譓賰ドイツの輸出総額のなかで植民地との貿易の割合は小さい
(C) ドイツの中東地域への経済進出
・1880年代および1890年代にトルコへ進出した→バグダート鉄道の建設を中心に行われ
た→鉄道建設を中心に,
貿易活動, 綿花と小麦の栽培,
灌漑施設の建設,
石油の試掘
→中東地域はドイツ帝国主義にとって重要な経済領域になった。
(D) 植民地政策推進の内政的な原因--社会帝国主義の概念をめぐって---
・ハンス・ウルリヒ・ヴーラーの社会帝国主義の概念譓賰帝国主義は経済的要請(国内
の工業と農業の発展のためには海外への経済領域の拡張が必要)と政治的社会的要請
(経済を安定化させることにより社会体制の権力関係の安定化に役立つ)による。
(2) ドイツ社会民主党および第二インターナショナルにおける植民地政策論争
(A) 植民地政策論争の展開
(1) 1900年マインツ党大会における「
世界政策に関する決議」(ドイツの中国への出兵とブーア
戦争に反対する決議)
(2) 1903年ドレスデン
党大会および1904年ブレーメン 党大会での討議
(3) 第二インターナショナル
のロンドン大会(1896
年) およびパリ大会(1900
年)
における植民地問題に
対する態度。
(4) 1904年アムステルダム
国際社会主義者会議におけるファン=コルの問題提起
(5) 1907年シュツットガルト国際社会主義者会議の植民地問題委員会での論争
(6) 1907年シュツットガルト国際社会主義者会議の総会における植民地問題を巡る論争と決議
(7) 1907年SPD
のエッセン党大会における植民地主義をめぐる論争
(B) 植民地政策論争の争点
(1) 社会主義的植民地政策か植民地政策原則的拒否論か
(2) 植民地政策は生産力開発的,
文明促進的作用を持つかどうか。
(3) 植民地における資本主義発展は,そこでの社会主義実現の前提条件であるのか。
(4) 植民地の民族運動をどう見るのか。
(3) 第二インターナショナルの理論家たちの植民地政策論
(A) カウツキーの植民地政策論と帝国主義認識
(1) K.Kautrsky, ltere und neuere kolonialpolitik, in; Die Neue Zeit, XVI-1,189
7/8. 労働植民地と搾取植民地の区別。
自由貿易主義的植民地政策から,新植民地
政策への転換(1880
年頃以後)。
K.Kautsky, Schippe, Brentano und die Flottenfrage, in ;Derselbe,XVIII-1,1900
(3)K.Kautsky, Sozialismus und Kolonialpolitik, 1907.→ 搾取植民地を旧式搾取植民
地(
重商主義期の旧植民帝国)
と新式搾取植民地(1880
年代に始まったアフリカと中
国に注目する植民地政策の新時代)
にわけ,後者により帝国主義を分析。
カウツキー
の当時の資本主義についての見方は,
独占体制は資本主義の崩壊を延期させるが,
結
局,
それだけよけいに恐るべき崩壊をもたらすだろうということにあった。(
資本主
義発展=
崩壊像の枠内に,「軍国主義」「カルテル・トラスト体制」「資本輸出と結合した
新型搾取植民地」
などを位置づけるもの)。
(B)バウアーの「
資本主義的膨張政策」
論と「 経済領域」
論
(1) Otto Bauer, Nationalit tenfrage und Sozialdemokratie, Wien 1907.
民族原理が自由主義時代,
帝国主義時代, 社会主義社会においてどう変化するか論じ,
その際,
保護関税の機能,「資本主義的拡張政策」「経済領域」
なども論じた。
(C) ヒルファデイングの植民地政策論
(1) 1907年の植民地政策論
・1907年の帝国議会選挙・・・
SPD は1903年選挙よりも約25万票の得票数の増加にもかか
わらず,
議席の半分を失った。これは決選投票時のSPD
の孤立による。また,自由主
義諸政党も宰相ビューローの植民地政策遂行を支持するにいたった。
・Hilferding,
Die deutsche Imperialismus und die innere Politik, in;NZ.XXVI-1
1907. →世界情勢のなかでのドイツ帝国主義の歴史的特質を明らかにし,
さらにブロ
ック政策のもとでのドイツの内政の現状を分析した。→ドイツ帝国主義の実行不可能
性から,
ドイツがヨーロッパ戦争を引き起こす必然性があることを主張。
(2) 第二インターナショナルのシュツットガルト大会(1907
年)
に関連して
・R.Hilferding,
Der Internationale Kongress in Stuttgart, in; NZ.XXV-2,1907.
ブルジョワジーの民族意識は,
排外主義となり,
国際性を持ちえないのに対して,
プ
ロレタリアートの民族意識は,
かれらの「 階級意識の同等性」
と「 利害の共同性」
の
ために,国際性を持ちうると主張。
( 現実には,第一次大戦の勃発時に,第二インタ
ーナショナルの各国の政党は,
民族主義に屈伏した
)。 また,軍国主義に対する態度
( 民兵制の提唱,
戦争防止の努力)。さらに,植民地問題に対する態度(
植民地が, 資
本主義の延命に連なり,労働者の階級利害に反すること,および植民地の搾取と原住
民の奴隷化をもたらすという,
二つの理由から,
植民地政策に反対した)。
(3) 『金融資本論』(1910
年) における植民地政策論の転回
・同書の第22章における植民地政策論の特徴は,植民地政策と資本輸出との関連が明ら
かにされたこと,「経済領域」 という新しい概念が使用されたことにある。(
←パルヴス,
バウアーの影響)。→ 帝国主義を経済領域の拡張をめぐる先進資本主義諸国の間の闘争と
捉えた。
・ヒルファデイングの帝国主義認識は,カウツキーの見解に従った1907年の植民地政策
論から,
バウアーとパルヴスの影響のもとに,1910年には「 経済領域拡張闘争」
論へ
の転回がなされた。
譓→ ヒルファデイングは,植民地政策を,保護関税政策や資本
輸出とともに,金融資本の経済政策の一環をなすものと捉え,
これらの経済政策の総
体としての帝国主義を拒否した。
(3)帝国主義論の類型
(1)資本蓄積論的帝国主義論
(1)『金融資本論』(Das
Finanzkapital,1910)における帝国主義論の構造
・ヒルファデイングが,『金融資本論』を書くにあたって,果たさなければなら
なかった課題は,ひとつには,資本の集積・集中の結果として,どのような資本形態が支
配的資本として成立したのか明らかにすること,二つに,帝国主義諸現象を総体的に把握
し,かつそれが新段階の資本主義の蓄積運動から必然的に生じた物であることを論証する
こと,三つに,この資本主義の最高の発展とその結果としての帝国主義が社会主義革命の
前提条件をなすことを示すことなどであった。
(A)
金融資本範疇とその矛盾
・金融資本の成立の論理を,産業における独占形成の論理と,銀行の産業支配の論理と
の統一として捉えた。
(独占形成の論理)資本制生産の発展→資本の有機的構成の高度化と固定資本の巨大
化→平均利潤率の成立の阻害→これを克服するものとしての株式会社制度の導入→重
工業部門への資本の流入は容易になる→この部門において利潤率が平均利潤率以下に
低下し,これが継続する傾向→カルテル・トラストなどの独占的資本組織の発達。
(銀行の産業支配の論理)銀行の機能が支払い信用(流通信用),資本信用,発行業
務と進むにつれて,銀行の産業支配は進展→資本信用とりわけ固定資本信用の供与に
より銀行の優位は強まる→銀行の資金の固定化は株式会社制度の採用により克服され
る(資金の流動化)→銀行は発行業務により貸し付けた資金の回収と創業者利得の獲
得可能→銀行と産業企業との人的結合が生じる。譓蠇→金融資本の成立
・金融資本の定義・・・・「
現実には産業資本に転化されている銀行資本,
したがって貨幣
形態における資本を,わたしは金融資本となずける」(『金融資本論』第3
編第14章)
・ヒルファデイングの金融資本範疇に対する評価。
(B)
資本主義の内面的変化と帝国主義の構造
・資本主義の内面的変化(自由競争から独占への変化)を,金融資本を基軸に把握し,
新段階の資本主義の蓄積運動や恐慌の変化,帝国主義などを解明した譓→資本主義の
一般的な法則の延長線上で帝国主義を捉えようとした。・・・・・
内在的要因からの説明
・他方で,世界資本主義の構造変化から,金融資本主義と帝国主義の成立を説くという
論理も見られる。蠇→論文「ドイツ帝国主義と国内政治」において,世界資本主義の
構造が,イギリスの産業資本を中心とした国際的自由貿易の体制から,
「
イギリスの
工業」 とヨーロッパの産業資本主義との競争する世界体制へと変化し,
これにともな
って,
植民地をめぐる対立などの帝国主義的対立が生じたと説明した。・・・・外在的要
因からの説明。
・「帝国主義政策の土台」と「帝国主義のイデオロギー」
(C)
帝国主義の諸政策と段階。帝国主義の必然性。
・ヒルファデイングの帝国主義観=帝国主義の諸政策が互いに内的関連のある総体と把
握され,かつ,それが資本主義の内面的変化から生じた結果と捉えられている→政策の
総体即段階という把握。
(D) プロレタリアートの帝国主義に対する態度
(2)ヴェ・イ・レーニン『資本主義の最高の段階としての帝国主義』(1917)
第一章 生産の集積と独占
(1) 大規模な企業への生産の集中==資本主義の特徴譓→集積は一定の段階で独占に接近す
る譓→
競争から独占への転化(
ドイツのカルテルとアメリカのトラストについての
実例の呈示)
譓→生産の社会化の巨大な前進(
技術上の発明や改良の過程の社会化)
==完全な社会化への過渡期(
生産は社会的だがで取得は私的)
譓蠇→ 社会主義(?)
第二章 銀行とその新しい役割
(1) 銀行業務の発展と少数の銀行への銀行業務の集積譓→銀行は仲介者という役割から,
全能の独占者になる(
一国の貨幣資本と生産手段を支配する)
→銀行トラスト, 独占
(2) 銀行の資本の集積
(預金の集積, 銀行集団の形成, 取引の集積) → 産業企業への支
配の強化
→ 資本の集積と独占の形成の過程を促進する
→ 銀行資本と産業資本
の融合・ 人的結合譓→
自由競争と独占の混合物という過渡的な資本主義の成立
第三章 金融資本と金融寡頭制
(1) 金融資本の概念==「 生産の集積,
そこから発生する独占,
銀行と産業との融合あるい
は癒着譓蠇賰これが金融資本の発生史であり,金融資本の概念の内容である。」
(2) 資本主義的独占の支配から金融寡頭制の支配へ譓蠇賰参与制度による親会社の子会社
支配の進展譓蠇賰金融資本は,
会社設立,
有価証券の発行, 国債の引受などにより,
巨額の利潤を獲得し,
金融寡頭制を強化する。 土地投機も金融資本の有利な業務。
(3) 資本の所有と投資の分離,
貨幣資本と生産資本との分離,
金利生活者と企業家・ 経営
者との分離が,巨大な規模に達している段階の資本主義譓→帝国主義,
金融資本支配
第四章 資本の輸出
(1) 自由競争の支配する資本主義から独占の支配する資本主義→商品輸出から資本輸出
(2) 過剰資本の発生→資本輸出の必然性
(3) 資本輸出の効果→輸出国の商品輸出を促進する。輸出相手国の資本主義の発展を促進
第五章 資本家団体の間での世界の分割
(1) 資本家たちの独占団体譓蠇まず,国内市場の分割,
ついで世界市場の分割譓→国際
カルテルの形成。
( 例譓蠇賰電気工業,A.E.G.
とG.E.)
(2) 石油業譓蠇賰ロックフェラーとロスチャイルド譓蠇賰ドイツの銀行を中心とした企業
家グループの対抗。
海運業, 国際軌条カルテル。
(3) 資本家団体の間での世界の分割譓→
諸国家の間での世界の領土的分割
第六章 列強の間での世界の分割
(1) 世界的植民地政策の時代譓蠇賰植民地獲得のための闘争の強化は,金融資本の時代に
みられるものかどうか。世界はどのように分割されているか。
(2) 植民地政策,
帝国主義そのものは古代にも存在した。→
資本主義的帝国主義の時代
の植民地政策(
金融資本による世界の経済的分割)
は,国家的従属のいくたの過渡的
形態を作りだす(
植民地, 影響圏,
経済領域)。
第七章 資本主義の特殊の段階としての帝国主義
(1) 帝国主義の定義譓蠇「
帝国主義とは資本主義の独占的段階である」(
「 金融資本は
産業家の独占団体の資本と融合している独占的な少数の巨大銀行の銀行資本である」
ことと,「 徹底的に分割されつくした地球上の領土の独占的領有という植民地政策へ
の移行」 という二つを含む)。
(2) 帝国主義の5つのメルクマール譓蠇蠇生産と資本の集積,金融寡頭制の成立,資本輸
出が重要になったこと,国際的な資本家の独占団体による世界の分割,列強による地
球の領土的分割。
(3) カウツキーやホブスンの帝国主義論にたいする批判。
(4) 帝国主義戦争の必然性(
資本の蓄積と領土の分割との間の不均衡を除去する手段)
第八章 寄生性と資本主義の腐朽性
(1) 帝国主義的寄生性譓蠇金利生活者の支配譓蠇イギリスにおける金利生活者の増大と生
産人口の比率の減少譓蠇賰プロレタリアートの一部の労働貴族化。
第九章 帝国主義の批判
(1) 帝国主義の批判譓蠇賰帝国主義の政策にたいしてとる態度。
(2) 社会帝国主義に対する批判
(3) カウツキーの改良主義(
帝国主義の基礎の改良主義的な改変)
への批判。
(4) カウツキーの超帝国主義への批判。
(5) 『金融資本論』におけるヒルファデイングの帝国主義に対する態度への評価。
第十章 帝国主義の歴史的地位
(1) 帝国主義の歴史的地位の規定譓蠇賰それは独占資本主義である,独占は生産の集積か
ら生じた,
原料資源の独占, 独占は銀行から生じた,
独占は植民地政策から生じた。
V.I.レーニンは,ヒルファディングの『金融資本論』とホブスンの『帝国主義研究』の
影響のもとに,その帝国主義論を形成した。ヒルファディングの理論に基本的に依拠して
いるが,その貨幣論の流通主義的誤りを指摘し,金融資本の生産的基礎を強調し,また,
帝国主義を政策体系としてよりは資本主義発展の必然的な一段階として捉えた。
(2)
世界市場論的タイプの帝国主義論
(A)パルヴス『植民地政策と崩壊』(1907)
(B)ルクセンブルク『資本蓄積論』(1913)
・ルクセンブルクは,
修正主義論争の時以来,
資本主義崩壊論の信奉者であり,
『社会改
良か革命か』においては,
世界市場の完成とともに,
資本主義崩壊をもたらすような過剰
生産恐慌が到来すると論じた。しかし,
この『資本蓄積論』(1913)においては,マルクス
の再生産論を批判し,資本蓄積(拡大再生産)の際には,剰余価値の実現のために資本主
義領域以外に非資本主義領域の購買者を必要とするとみなし,資本主義国が非資本主義領
域を侵食してゆく過程を帝国主義だとみなした。
[同書の内容]
第一篇 再生産の問題
第二篇 問題の歴史的叙述
第三篇 蓄積の歴史的諸条件
第一篇では,ケネー,スミス,マルクスの再生産論について論じ,拡大再生産においては
蓄積されるべき剰余価値部分が実現されるためには,生産諸部門の間の均衡以外に,商品
にたいする支払い能力のある購買者が必要であると論じた。第二篇では,資本蓄積の可能
性をめぐる三つの論争を検討した。第三篇では,有機的構成の高度化と剰余価値率の増大
を考慮した拡大再生産表式を作成し,これが不均衡におちいることを証明し,資本主義生
産領域のみを前提にしては,拡大再生産は進行しないと論じた。そして,資本蓄積(拡大
再生産)が順調に進展するためには,資本主義社会の購買者以外に,非資本主義的な購買
者が必要だと論じた。そうした非資本主義的購買者は,小農民や手工業者などの単純商品
生産者,あるいは資本主義国以外の発展途上国における非資本主義的な人々である。帝国
主義とは,先進資本主義国がそうした非資本主義的領域の獲得をめぐって,政治的に争う
ことだと見なされたのである。
引用文
(1) 世界交易の意義
「こうして,
剰余価値が生産される各生産期間と,
剰余価値が資本化される,それに続く
蓄積との間には,二つの異なる取引譓蠇賰剰余価値のその純粋な形態への転化すなわち実
現とこの純粋な価値姿態の生産資本姿態への転化譓蠇賰が横たわっているのであって,こ
の二つの取引は,資本制生産とそれをとりまく非資本制的世界との間でなされる。だから
剰余価値の実現ならびに不変資本の諸要素の調達という二つの見地からすれば,世界交易
譓蠇与えられた具体的諸関係のもとでは,本質的には,資本制的生産形態と非資本制的生
産形態とのあいだの交換である世界交易は,もともと,資本主義の歴史的な環境条件であ
る。」(ルクセンブルク,長谷部訳,『資本蓄積論』下,422
頁)
。
(2) 非資本性的環境の意義
「だが,
われわれの見るところでは,
資本主義は, その十分な成熟においてさえも,
あら
ゆる連関において,
非資本制的な層および社会の同時的実存を頼りにしている。この関係
は,
『過剰生産物』にとっての販売市場という赤裸々な問題譓蠇蠇この問題は,
シスモン
ディやその後の資本制的蓄積の批判者および懐疑論者によって提出されたものだが譓蠇
によって尽きるものではない。資本の蓄積過程は,
その一切の価値関係および物象関係
譓蠇賰不変資本,
可変資本, および剰余価値譓蠇蠇によって非資本制的な生産諸形態に結
び付けられている。この後者は,
かの過程の,
与えられた歴史的環境をなす。資本蓄積は
資本制的生産様式の排他的かつ絶対的な支配という前提のもとでは叙述されえないもの
であって,
それはむしろ, 非資本制的な環境なしにはどの点でも考えられないものであ
る。」(
同,430頁)
。
(3) 内部的市場と外部的市場
「・・・資本制的生産の見地から見た内部的市場は,
資本制的市場であり,
それ自身の生
産物の購買者,
およびそれ自身の生産要素の注文先としての,
その生産そのものである。
資本にとっての外部的市場とは,
資本の生産物を吸収し,
資本に生産要素と労働力とを提
供する,
非資本制的な社会環境である。この見地からすれば,
すなわち経済学的には,
ド
イツとイギリスとは,
その相互の商品交換においては,
たいていの場合には,
内部的すな
わち資本制的市場であるが,
ドイツの工業とドイツの農民的消費者ならびに生産者との交
換は,
ドイツの資本にとっては,
対外的市場関係である。・・・内部的な資本制的交易に
おいては,
せいぜい, 社会的層生産物の価値のうちの一定部分譓蠇蠇消耗された不変資本
可変資本,
および剰余価値の消費部分譓蠇蠇が実現されるにすぎない。これに反して,
剰余価値のうち資本化されるべき部分は,
『外部』で実現されねばならない。」(
同,432
以上のように,帝国主義に関するマルクス主義学派の理論としては,ヒルファディング
やV.I.レーニンの帝国主義論に示されるように,金融資本の資本蓄積様式から帝国主義の
必然性とその政策を説く理論と,ルクセンブルクやパルヴスに見られるように,世界市場
の構造のなかで複数の先進工業地域の成立とともに帝国主義政策の必然性がもたらされた
とする理論と,両者を折衷したカウツキーの理論とが存在した。また,これらの帝国主義
論は,何らかの意味で,資本主義の崩壊の必然性を説こうとする意図を秘めていた。
これにたいして,シュムペーターの帝国主義論は,資本主義そのものには帝国主義への
傾向は内在しておらず,資本主義以前の封建的勢力の領土拡張への衝動から帝国主義政策
は発生するとみるのであり,また,イギリスのホブスンは資本主義のなかの一部の金融業
者や冒険的な商業資本家が帝国主義政策を好むとみた。したがって,資本主義そのものに
帝国主義に向かう必然性は無く,産業資本は合理的で平和的な政策を好むと見たのである
これらの見解は,帝国主義に関する自由主義的な理論と見ることができる。マックス・ウ
ェーバーなども,かれらと同じような帝国主義観をもっていたの見られるのである。
[II]
ヴァイマル共和国期のヒルファディングの組織資本主義論
(1)ヒルファディングの組織資本主義論の成立と発展
1.現代の問題状況
A. ヒルファディングの組織資本主義論にたいする従来の評価
B. 加藤栄一,
玉垣良典などの評価.
C. ドイツの比較社会史学派の人々
( H.U.Wehler, J.Kocka, H.A.Winkler ) などによ
る評価と批判.
(1) 組織資本主義はファシズム的政治支配形態をもたらすという経済決定論が見られ
,国家の自立性と独自の役割が看過されている.
(2) 金融資本による組織化と国家による組織化とが区別されていない.
(3) 前資本主義的要因の役割が不明確.
2.『金融資本論』(1910)における組織資本主義論の萌芽
A. 金融資本による全経済の組織化という見通し--→組織資本主義論の萌芽.
(1) カルテルによる生産の組織化という見通し
各産業分野へのカルテル(
独占的利益協定) の普及譓蠇→「全資本主義的生産」を
「意識的に規制」し,「すべての生産部面において生産の大きさを決定する」「総
カルテル」の成立.
(2) 中央銀行は「社会の全貨幣の処理権を持つ」譓蠇→
銀行の全社会的生産にたい
する管理を可能にする.譓蠇→
第一編,
第二編, 第三編のいずれも,
銀行の産業
支配したがって金融資本による全社会的生産の管理という指摘をもって終わる.
(3) ヒルファディングは,ゼネラル・カルテルの成立により,
資本主義生産の組織化
を論証しようとしたが,
それだけでは不十分だと考え,
銀行が信用関係をつうじて
産業を支配し,
かくして社会的生産を管理するという論理を主軸にして,
資本によ
る生産の社会化を論証しようとした.
B. だが,『金融資本論』の第五編では,同書の結論として帝国主義戦争と社会的動乱
の到来を強調.
3.1910年から第一次大戦までの理論の発展
A. 大戦直前の論文「組織権力と国家権力」(
Organisationsmacht und Staatsgewalt
in; Neue Zeit, 33. Jg., Bd.2, 1913/14 ).
(1) 大銀行やカルテルなどの経済組織が,
国家権力に並ぶ組織になる譓蠇→
カルテ
ル,
トラストなどの資本主義的独占が国家の政策の機能を変化させたり,廃止でき
るようになる譓蠇→
経済の構造や法則を変化させる.
(2) カルテル譓蠇→
自由競争を変化させ,法体制を変化させる.
(3) 大企業,
カルテル・トラストなどは,社会的な生産であり,組織された生産とい
う社会主義社会の条件に適合しているとみる譓→資本主義的組織化に肯定的な態度
B. 大戦中の論文「諸階級の労働共同体か」(Arbeitsgemeinschaft
der Klassen ? in;
Der Kampf,8.Jg.,1915)
(1) 資本主義の組織化の進展と労働運動の改良活動の進展譓蠇→
労働者の物質的状
態の改善譓蠇→
かれらの革命への衝動を弱めた譓蠇→
労資協調的傾向の成立.
(2) 「少数の大銀行による独占的に組織された工業にたいする支配である金融資本は
生産の無政府性を弱化させる傾向をもっており,無政府的な資本主義的経済体制か
ら,
組織された資本主義的経済体制への変化の萌芽をはらんでいる.
金融資本とそ
の政策が生み出した国家権力の著しい強化も同じ方向に作用する.
社会主義の勝利
の代わりに,
たしかに組織されてはいるが,支配に適した,
非民主主義的に組織さ
れた経済体制が可能になるようにみえる」譓蠇→「帝国主義的権力政策」に対抗
し,
「内政と外交の民主主義的改良」を図る思想は後退し,
「社会改良的政策によ
る直接的な物質的利害の充足」を図る思想が支配的になってきた譓蠇蠇→
この傾
向と対決することが
, SPD の緊急の課題だとみた.
4.ドイツ革命期における社会化論と組織資本主義論
A. 第一回経営協議会での報告「社会化と諸階級の勢力関係」(Die
Sozialisierung
und die Machtverh ltnisse der Klassen, Referat auf den 1.Betriebskongress
gehalten am 5. Oktober 1920)
(1) 当時の階級情勢の分析から始め,
炭鉱業の完全社会化から全産業の社会化への展望
を示そうとした.そのなかで,資本主義の組織化傾向について述べた.
つまり,も
っとも重要な産業部門において生産が一群の大経営に集中(
第一段階),カルテル・
トラストによる競争の制限や排除(
第二段階),大工業と大銀行の結合の強化(
第三
段階).
(2) 経済の組織化傾向は不可避的とみながらも,労働者階級にとって重要な問題は,
「この経済が資本主義的階層制的に組織されるべきか,それとも民主主義的社会主
義的に組織されるべきかという問題である」譓→資本家を排除し基幹産業の社会化
を図り,
自己管理団体によるそれの管理・運営をつうじて,「社会主義的民主主義
経済」の実現を図るべきだと考えていた.
(3) 社会化の形態としては「国有化つまり生産の官僚制化」を拒否し,「社会主義的
生産部門を産業の自己管理団体つまり産業議会により管理」する.
社会化の内容
としては,原料,
動力, 鉄鋼業,
大土地所有の社会化をあげた.
B. G.D.H. コール『産業における自己管理』(
ドイツ語版,
1921) へのヒルファディ
ングの序文
(1) ヒルファディングの社会化論から組織資本主義論への転換の思想行程を示す.
(2) ロシア型の社会主義建設とは異なった社会主義化のありかたを示している譓蠇→
オットー・バウアーの『社会主義への道』で論述され,1918年のドイツ社会化委員
会に提出された構想,
つまり生産者, 消費者, および国家の代表より構成される自
己管理団体による,
社会化された経済部門の管理という構想を肯定譓蠇→
社会主
義的民主主義的経済の実現.
(3) イギリスのギルド社会主義の思想にたいする評価譓蠇蠇→
それは国家ではなく労
働組合が社会主義実現のための組織形態だとみなし,ゼネストなどの革命的手段に
よって直接に生産点を掌握することが必要だと考えた.
その国家論・革命観を高く
評価.
(4) 他方,
国家権力と並ぶ大経済組織(
企業家組織と労働者組織)
が成立する譓蠇→
一国の経済政策は国家によってのみ決定されず,企業家組織と労働者組織との間の
協定によって調整される譓蠇蠇→
労資共同体の理念(
労資の協力活動による労働
者の経済的および政治的状態の改良という改良主義の思想)
.
(5) ヒルファディングとしては当時,
この労資共同体論という改良主義の思想にたいし
て,
重要産業の社会化と自己管理団体によるその管理という社会化構想を対置.
5.ヴァイマル共和国期,とりわけ1923-33年におけるヒルファディングの組織資
本主義=経済民主主義論
(1) 金融資本による資本主義の組織化の進展により,「敵対的な形態で階層的に組織さ
れた経済」が成立するだろうとする見通し譓蠇→
組織資本主義論の成立.
(2) 社会民主党,
労働組合, 協同組合,
あるいは労働者の経営参加などにより,階層制
的資本主義経済を「民主主義的に組織さた経済」へ転換すべきだという経済民主主
義を提唱譓蠇蠇→
社会改良主義の思想を強調.
A. 論文「この時代の諸問題」(Probleme
der Zeit,in; Die Gesellschaft,1-1,1924)
(1) 1914年以来十年間の社会発展を分析し,
経済過程や政治関係の変化,
国家と国民と
の関係,
国際関係の変化の外交政策におよぼす作用など三つの論点を考察.
(2) 資本の集積傾向の進展と金融資本による諸資本の統一により,
「自由競争の資本主
義から組織された資本主義への移行」がなされると予想蠇→
組織資本主義の下で
は資本主義の無政府性の克服がなされる譓蠇蠇→
「たしかに組織されてはいるが
, 敵対的な形態で階層的に組織された経済」が生じる.
(3) 敵対的な形態の組織資本主義とはなにか譓蠇蠇→
「生産手段を所有している諸階
層のために,
社会的生産諸力を規制し組織しようという試み」譓蠇蠇→
具体的政
策としては,「大トラストによる新投資の計画的配分,
好景気の時期の固定資本の
新投資の一定の抑制,
沈滞期へのそれの延期,
中央銀行の適切な貨幣政策に支持さ
れた大銀行による状況に適した信用調整」等譓蠇→資本主義経済の安定化の政策.
(4) こうし資本主義の組織化の試みと私的所有のもつ敵対性との矛盾譓蠇→
民主主義
的に組織された経済つまり生産者大衆による経済の規制により解決譓蠇→
経済民
主主義のための政策「工場民主主義,
経営協議会の地位の強化,
あらゆるニュアン
スの包括的な意味の生産管理」譓蠇→
経済民主主義の実現.
B. ドイツ社会民主党のキール党大会での報告「共和国における社会民主党の任務」
(Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik. Rede auf den Parteitage
SPD zu Kiel, Berlin 1927 )
(1) 組織資本主義が現実のものになったと確認されている.「決定的なのは,
われわれ
が目下,
資本主義の一定の時期に・・・生きているということであり,われわれが
・・・諸力の自由に運動する経済から組織された経済にいたっていることである」
(2) 新しい生産技術の発明,
企業組織の国内的および国際的な独占的経済組織への発展
により,「組織資本主義は現実には,
自由競争という資本主義的原理を,
計画的経
済という社会主義的原理によって,
原則的に置き換えることを意味している」譓→
組織資本主義にたいしてより肯定的に評価している.
(3) 経済民主主義も民主主義国家により実現されるとみた.
つまり「われわれの世代は
国家の援助により,意識的で社会的な規制の助けにより,
この資本家によって組織
され,管理された経済から,
民主主義国家によって管理された経済への変革という
課題をたてる」と.
(4) 民主主義への高い評価譓蠇蠇→
議会制度により多数派を形成し,国家意志を左右
することがプロレタリアートのとるべき路線という.
6.ヒルファディング組織資本主義論の意義と限界.
A. 政治的多価のテーゼに関連して,
ヒルファディングにあっては「組織化の進展」は
「必然的に権威主義的ファシズム的な政治的支配形態に導くといった,経済と政治
とをナイーブに等置する還元主義的な把握がみられる」という批判についてはどう
か。蠇蠇→『金融資本論』(1910)では, 金融資本の完成形態においては,
資本貴族
の独裁が完成するという一節がみられ,経済決定論な見解がみられる。しかし,ヴ
ァイマル共和国期の組織資本主義論・経済民主主義においては,階層制的資本主義
的経済になるか民主主義的社会主義的経済になるかは,
労働者の活動如何にかかっ
ているという立場であり,経済決定論とはいえない。
B. 経済から相対的に自立した国家の独自な役割が看過されているという批判はどうか
蠇蠇→『金融資本論』(1910)からドイツ革命期までは,
階級国家論にたち,国家の
独自性という把握はみられない。しかし,ヴァイマル共和国期には,民主的国家に
より組織資本主義に干渉し,これを民主主義的社会主義的経済に変革すべきだとい
うのであるから,
国家の独自性が認められていたといえる。
C. 金融資本による組織化と国家による組織化とを区別しないという批判はどうか蠇→
国家による資本主義の組織化という認識はよわい.
D. 前資本主義的要因の認識が弱いという批判はどうか蠇→金融資本による支配に対す
る批判に比べて,
前資本主義的要因についての分析はよわい.
E. 「組織化の意義をなによりもまず(
資本主義の)
無政府性の克服に収斂させて考え
ている」という批判はどうか。蠇→資本主義のもとでの組織化の進展を無政府性の
克服とみて,それがただちに,社会主義的計画性を意味するとみる誤りがある.
F. ヒルファディング組織資本主義論の意義と限界.
[III]第三帝国期におけるフリードリヒ・ポロックの国家資本主義の理論
(1)ポロックの国家資本主義の概念
(1) 第一次大戦後の資本主義,とりわけナチス経済およびニュー・ディール期アメリカ資
本主義を念頭において,国家資本主義というモデルを構築した。譓蠇→理念型
(2) 市場経済ないしは競争的資本主義との比較で,国家資本主義の特徴を明らかにしよう
とする。市場経済においては,市場における価格変動を通じて,需要と供給とが調整さ
れるが,国家資本主義においては,国家の一般的な計画によって消費と生産とが一致さ
せられている。
(3) 国家資本主義と私的資本主義との相違点譓蠇→国家資本主義は,利潤に関心をよせる
者が重要な役割を果たす限りでは,資本主義としての性格を依然として保持しているが
,市場ではなく国家の統制が生産と分配の調整をおこなう限りでは,競争的資本主義の
重要な特徴を失っている。国家資本主義は,国家の直接の経済統制によって,
競争的資
本主義の市場機能の制限を,
より完全なものにする。
(4) 国家資本主義の特徴譓蠇→国家の一般的計画が,
生産, 消費,
貯蓄,
投資等に関する
指令を出し,個別企業や企業グループの利害関心も,この一般的計画に従属させられ,
無計画な生産の代わりに科学的管理が支配するようになる。価格はもはや「経済過程の
主人としては働かず」,むしろ管理される。また,国家の一般的計画は国家権力によっ
て強制され,市場法則には任せられていない等の事態である。
「 政府の介入」
や「 政府
による引受け」 や
「政府による統制」
が強調されている。政府の一般的な計画に従った
干渉によって,
景気の調整とか雇用問題等の重要な経済問題の解決はなされる。
(5) 国家資本主義は,競争的資本主義でも独占資本主義でもなく,さらに,社会主義でも
ない,新しい体制なのであり,その特徴は国家による一般的計画にもとづく,
経済に対
する干渉という点にある。
(2)国家資本主義の二つの類型と段階概念としての国家資本主義
(1) ポロックは論文「
国家資本主義」 のある箇所において,国家資本主義を独占資本主義
のつぎの段階と想定している。大内力は,管理通貨制度の成立とその下での完全雇用と
景気調節を目指した財政・
金融政策や経済政策の採用による「経済の国家管理」をもっ
て,国家独占資本主義の成立のメルクマールとし,
帝国主義段階の一つの過渡的な段階
とみなしたのである(3)
が,ポロックの国家資本主義論はこの大内力の国家独占資本主
義論に似た資本主義観を取りつつも,これを独占資本主義に続く資本主義の新段階と捉
えるものである。
(2) 国家資本主義の次の段階譓蠇蠇→具体的には論じていないが,
国家資本主義のつぎの
段階として,社会主義的計画経済が考えられていることは充分に,
推測される。という
のも,論文「資本主義の現状と新計画経済体制の新計画経済体制の見込み」において,
全面的な計画経済を意味する社会主義的計画経済の優越性を,
主張しているから。
(3) 計画経済に対する疑念として一般に挙げられているもの===
ひとつは,「今日の市場
経済よりも,
生産的ではないという疑念」(4)
であり,いまひとつは,「 計画経済にお
いては,利潤追求と自由競争という決定的な推進力が,
欠落してしまい,
経済の多産性
が失われるということである」(5)
。 譓蠇蠇→(
前者への反論)
交換によるとは別の仕
方で,
経費と収益 との関係を確定する可能性はすでに今日の経験の基礎上で与えられ
ている。(
後者への反論) この異論は根拠のない心理学に基づいている。譓蠇→計画経
済の可能性と市場経済にたいするそれの優越性を確信。
(4) ポロックの計画経済観をめぐって。
(3)ポロックの国家資本主義概念の評価
(1) このポロックの国家資本主義論を,どのように評価すればよいのだろうか。譓蠇蠇→
1930年代における市場経済から計画経済への志向が,1970年代以後には,とりわけ,
ソ
連邦と東欧の共産主義政権の瓦解後は,逆に,
計画経済から市場経済への復帰へ,
ヴェ
クトルが変化してきた。譓蠇蠇→こうした状況の下にあっては,ポロックの市場経済批
判と計画経済の提唱論は,時代後れのようにみえるかもしれない。しかし,ポロックの
見解は,資本主義的な市場経済の限界を指摘したものとして,
また,資本主義の帝国主
義時代以後の発展を特徴づけるものとして,今一度,
検討する必要があるようにおもわ
れる。市場経済で全ての問題が解決するという幻想は持つべきでないのであり,また,
資本主義的市場経済そのものが,ナチス経済やニューディール経済にみられるように,
たえず,計画経済を導入し,
資本主義の修正を重ねてきたからである。
[IV]
組織資本主義論と国家資本主義論との比較
(1)資本主義の無政府性の克服をめぐって.
(1) 両者はともに,資本主義の無政府性の制限の進展に注目しているが,ポロックの国家
資本主義論では,国家の一般的な計画が経済の運動を規制するとされており,ヒルファ
デイングの組織資本主義論では,
経済そのものの自己組織化によって競争的資本主義の
無政府的生産が生み出す問題(
過剰生産とその結果)
が部分的にせよ克服されるとされ
ている。
(2) ヒルファデイングの組織資本主義論は,第一次大戦後のドイツやその他の欧米諸国の
資本主義の現実を,資本の集積・集中法則の貫徹によって進展する,カルテル・トラス
ト・コンツェルンなどの資本家組織の拡大強化を,独占化の進展というよりは,組織化
の進展という側面で評価する。つまり,市場における競争による価格の決定から独占価
格に変化することや,独占体による中小企業の支配,独占による普及化など,独占の作
用や弊害を強調するのではなく,自由競争の無政府的生産が組織的な生産に変化し,敵
対的ではあるが安定した経済が成立することを強調するのが,ヒルファデイングの組織
資本主義論であった。
(3) ポロックは,市場経済にかわる国家資本主義の新しい体制の特徴として,
「一般的な
計画が,生産,
消費, 貯蓄活動,
および資本投資に関する指令をだす」ことを挙げ,
欲
望の優先順位,
労働時間の大きさ,
消費されるべき社会的生産物の量,
生産拡大に回さ
れる社会的生産物のなどは,経済法則によって決定されるのではなく,
政治が決定する
とみている。 最後に,
経済に関する計画の遂行は,
国家権力によって強制され,
その結
果,
市場法則ないしその他の経済法則にはなにも重要なものがまかれさない。結局,
市
場経済の法則ではなく,
国家の経済活動に関する一般的な計画が,経済のあり方を規定
するのであり,そうした形で,
市場経済のもつ無政府性は克服されていると見ている。
(2)金融資本による組織化か,市場経済にたいする国家の一般的計画か。
(1) ヒルファデイングもポロックも,
市場経済のメカニズムにたいする不信感をもってお
り生産と消費の調整をはじめとする再生産上の諸問題は,
市場によっては解決できない
とみている。しかし,ヒルファデイングの組織資本主義論においては,今日のドイツの
比較社会史学派の歴史家たちが批判するように,
金融資本による組織化にみられる経済
そのものの論理による組織化は捉えられているが,
国家による組織化は捉えられていな
い。
(2) ポロックの国家資本主義論においては,まさに国家による一般的計画というものが,
国家資本主義の概念の基軸をなしている。国家の一般的計画が,国家の経済への干渉の
中心にあり,
これによって資本主義の諸問題は解決されるとされている。経済そのもの
の組織化よりも,国家による組織化が,
重視されていると言わなければならない。ここ
にポロックの理論の特徴がある。
(3)ヒルファデイングとポロックとの見解の共通点。
(1) 共通点譓蠇→金融資本による組織化によってであれ,国家による組織化によってでは
あれ,かれらはいずれも,競争的資本主義のもつ市場メカニズムが制限され,
市場メカ
ニズムとは異なる論理が経済を支配するようになると見ている。広い意味で,
競争的資
本主義が過去のものになり,
資本主義の組織化が進展していると見る点では,
共通して
いる。
(2) 相違点譓蠇→ヒルファデイングが専ら,経済そのもののなかに組織化への傾向があり
,これが市場経済の無政府性を克服する原動力だと見るのにたいして,ポロックは国家
の経済に関する一般的計画がそうした原動力だと見る点である。このように見ると,ヒ
ルファデイングの理論とポロックの理論とは資本主義の組織化傾向に関して,互いに,
補完しあう見解を提出したといえるのである。
(4)ヒルファデイングとポロックの見解の比較。
(1) ヒルファデイングの組織資本主義=
経済民主主義論は,ヴァイマル共和国期のドイツ
社会民主主義の実践を支えた理論であったが,
ポロックの国家資本主義論はそのような
特定の政党の実践を支えるための理論ではなく,
ナチス経済,
ニュー・ディール経済を
分析するための理論装置(理念型)
にすぎなかったことである。こうした資本主義への
態度という点で,
両者のあいだには相違がある。
(5)ポロックの国家資本主義論の意義と限界
(1) ポロックの国家資本主義論の特徴譓蠇→第一に,それが市場経済に対する計画経済の
優越性を主張している点にある。第二に,国家資本主義を独占資本主義に続く新しい段
階と見ている。第三に,国家資本主義を全体主義的国家資本主義と民主主義的国家資本
主義とに区別し,前者を自由の欠如した体制として批判し,後者を前者よりも相対的に
良いものと見なしている。第四に,国家の一般的計画による経済への干渉によって,市
場経済の法則が取って代わられたと見なしている。資本主義経済の自律的な経済法則が
,政治あるいは行政の論理によって交代させられたと見ている。
(2) ポロックの国家資本主義論の限界--→経済のもつ自律的法則の作用について,従
来の経済学説以上の解明する努力がなおざりにされた。国家の政策という政治的なもの
・主に論じられ,経済のメカニズムそのものの解明がなおざりにされている。
[V]現代資本主義を捉える概念をめぐって
(1)組織資本主義という概念について。
(1) 組織資本主義の概念は,現代資本主義のもっている,資本主義の元来もっていた無
政府的生産という特質を克服するという傾向を特徴ずけるものである。しかし,それは資
本主義経済の持っているダイナミズムを十分に説明しないという欠陥をもっている。資本
主義の組織化は,産業間の不均衡な発展や生産と消費の不一致などを克服し,恐慌の無い
安定した資本主義発展を可能にすると見なされており,そうした不均衡や不一致を孕みな
がら進行する資本主義的蓄積のダイナミズムを捉える論理が弱いからである。『金融資本
論』(1910)の第一編から第三編におけるにおける金融資本の蓄積様式に関する理論にも,
資本主義の安定化を予想する叙述が見られるが,
組織資本主義論はそうした資本主義理
解を前面に押し出しており,
そこにヒルファディングの資本主義理解の問題点がある。こ
うした限界に対しては,
金融資本の蓄積様式についてのより批判的な理論の発展が要請さ
れていると思われる。
(2)国家資本主義という概念について。
ポロックの国家資本主義の概念は,ヒルファディングの組織資本主義の概念を補完する
概念だと,評価できる。後者の概念において,国家による経済の組織化は殆ど触れられて
いないが,ポロックの概念においては,国家による経済の組織化が計画経済によりおこな
われるものと捉えられている。ポロックの国家資本主義論の特徴は,前述のように,(1)市
場経済にたいする計画経済の優越性を主張していること,(2)国家資本主義を独占資本主義
に続く新しい段階とみていること,(3)
国家資本主義を全体主義的国家資本主義と民主主
義的国家資本主義とに区別し,
後者を相対的にベターなものと見ていること,(4)市場経済
の法則が国家の一般的計画による経済への干渉に取って代わったと見ていること,
等であ
る。
ポロックの国家資本主義の概念において,
われわれは1929年の世界恐慌以来の,ナ
チスの完全雇用政策やアメリカのニューディール政策などの実践にはじまり,ケインズの
『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936)によって理論化された,
資本主義経済のマク
ロ経済政策に対する肯定的な評価を見ることが出来る。それは,
企業家団体による資本主
義の組織化と同様に,
資本主義的市場経済の無政府性を部分的に克服するという意味を持
つものであり,
その限りでは資本主義の重要な欠陥の一つを解決するものと見なされてい
る。しかし,ポロックによれば,ナチスの全体主義的な国家資本主義は,資本主義の無政
府性を克服しているものの,人間の自由を圧殺するという問題があるので,アメリカ型の
民主主義的国家資本主義の方がよい。民主主義的国家資本主義は,社会主義への一歩前進
であると評価しているように思われる。
結局,国家資本主義の概念は,現代資本主義にみられる国家のマクロ経済政策や諸々の
経済計画による資本主義の無政府性の部分的克服を肯定的に捉える点で,現代資本主義の
特徴の一つをうまく捉えていると,評価できる。しかし,この概念の場合にも,ヒルファ
ディングの組織資本主義の概念と同様の欠陥,つまり資本主義経済のもつ景気変動やもろ
もろの不均衡をともなった,ダイナミックな発展を十分に捉えていないという問題がある
組織資本主義と国家資本主義の概念は,いずれも,スタティックであり,ダイナミズムが
感じられないのである。これらの概念は,そうした欠陥を克服する必要がある。
(3)干渉国家および社会国家という概念について。
干渉国家あるいは社会国家という概念は,ヴェーラーなどの比較社会史学派の歴史家に
よって好んで用いられている概念であり,組織資本主義の時代における国家の特徴を示す
ものである。資本主義発展のなかで生じてくる諸々の経済問題,社会問題が,市民社会そ
のもののなかで解決できない場合には,国家がその経済政策や社会政策によって,それら
の経済問題,社会問題にたいして対処しなければならない。そして,組織資本主義の時代
の国家は,そうした干渉を行うための理論や政策を心得ており,そのための制度や機構を
もっているとみなされている。干渉国家といった場合には,経済や社会の危機(恐慌な
ど)にたいして,体制の維持のために干渉政策をおこなうという側面が重視されている。
他方,社会国家といった場合には,市民革命によって成立した近代国家が,元来は,市民
の自然権を守る法治国家としての性格を持っていたのに対して,資本主義発展にともなう
社会問題の発生にたいして,中間層や労働者階層の福祉・社会保障の政策を行うに至った
という側面が表現されている。
近代資本主義の市場経済機構は,19世紀中葉の競争的資本主義の時代には,比較的よ
く機能していたとみなされているが,19世紀末以来の帝国主義・独占資本主義の時代に
はいると,うまく機能しなくなり,国家は,まず,保護関税政策・植民地政策などの帝国
主義政策をとるにいたり,1929年の世界恐慌とそれに続く大量失業の時代には,アメ
リカのニューディール政策やナチス・ドイツの完全雇用政策がおこなわれ,ついで,ケイ
ンズによるマクロ経済政策の開発以来,各国政府はあるいは完全雇用の達成のため,ある
いは景気循環の安定化のために,財政・金融政策を用いるに至った。このように,資本主
義経済の市場機構の自立性に任せることが出来ず,国家が経済的社会的に干渉するという
のが,これまでの資本主義の実態であった。しかし,1970年代以来,そうしたケイン
ズに由来するマクロ経済政策が,失業問題の解決などにおいてうまく成果を挙げないとい
う状況のもとで,新自由主義や供給側経済学という新しい経済思想が台頭している。ふた
たび,干渉主義や社会福祉重視の経済学ではなく,スミスの古典派やマーシャルの新古典
派の信奉したような自由主義が復活している。旧社会主義国における市場経済への復帰も
そうした傾向に棹さすものであると言える。このような経済思想の対立のなかで,組織資
本主義と干渉国家との絡み合いについて,さらに研究する必要があるとおもわれる。
第二部
限界効用学派の成立からケインズ,シュムペーターまで
[I].限界効用学派の成立
1.限界革命とは何か。
1870年代に,ジェボンズ(William
S. Jevons,1835-1882),メンガー(Carl
Menger,1840-
1921),ワルラス(M.E.Leon
Walras,1834-1910) などの経済学者が,それぞれ独立に,限界
効用の概念を発見し,
価値論や分配論のような基礎理論を,
限界概念を用いて改革しよう
とした。これが,
限界革命だと言われている。
2.限界効用学派の諸派
イギリスのジェボンズが『経済学の理論』(The
thory of political economy,1871) で,
オーストリアのメンガーが『国民経済学原理』(Grundsaetze
der Volkswirtschaftslehre,
1871) で,
スイスのローザンヌでワルラスが『純粋経済学要論』(Elementes
d'economie
politique pure, ou theorie de la richesse sociale,1874-77)において,それまでの古
典学派が交換価値を説明する際に無視していた,財貨の効用という側面から,「限界効
用」により財貨の交換価値を説明しはじめた。ジェボンズは,最終効用度(final
degree
of utility)または最終効用(final
utlity)という用語を用い,
メンガーは「〔財の〕同
一部分量をもってもたらすことのできる諸欲望満足のうち最も重要さの小さいものが彼に
たいしてもつ意義」と定義し,
ワルラスは稀少性(rarete)または内包的効用(utilite
int
ensive) という用語を用いた。こうして,労働価値説から効用価値説への変化,
客観価値
説から主観価値説への転換が生じた。
3.限界効用とは何か。限界効用逓減法則と限界効用均等法則。
限界効用とは何か。古典学派やマルクス学派にとっては,商品の効用あるいは使用価値
とは,商品に備わった客観的な属性であったが,限界効用学派にとっては,効用とはその
商品が主体にもたらす楽しみや役立ちという主観的なものであった。つまり,効用とは消
費者が財の消費から得られる満足度を示す。消費者がある財の消費量を増加させてゆけば,
その財からえられる総効用は増加してゆくが,
財の追加一単位から得られる効用は減少し
てゆく。この際,
財の追加一単位から得られる追加効用を,
限界効用という。
そして,限界効用が,
財の消費量の増加とともに減少することを,
限界効用逓減法則と
いう。また,
消費者が自分の効用を最大にするようにもろもろの財の購入量を決定しよう
とする場合,
かれはそれぞれの財の限界効用が等しくなるように購入することによって,
最大の効用を獲得することができる。これを限界効用均等法則とよんでいる。この場合,
A 財の限界効用/A財の価格= B 財の限界効用/B財の価格= ・・・という公式が成立し,こ
れにより財の消費量と価格との関係がつけられる。
(1)
オーストリア学派
1.代表的理論家とその著作
A.メンガー
(Carl Menger,1840-1921)
『国民経済学原理』(
Grunds tze der Volkswirtschaftslehre,Wien,1871)
『社会科学とくに経済学の方法に関する研究』(Untersuchungen
ber die Methode der
Socialwissenschaften und der politischen konomie insbesondere,Leipzig,1883)
B.ボェーム=バウェルク(B
hm-Bawerk,Eugen von 1851-1914)
『資本および資本利子』(Kapital
und Kapitalzins,Insbruck 2 Bde.1884-89 ; 3.Aufl.
3 Bde.,1909-14 ; 4.Aufl.,3 Bde.Jena,1921) , 第一巻『資本利子理論の歴史と批判』(
Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien), 第二巻『資本の積極理論』(Positiv
e Theorie des Kapitals),第三巻『補論』(Exkurse
zur "Positive Theorie des Kapital
s")
『マルクス体系の終結』(Zum
Abschluss des Marxschen Systems.Berlin,1896)
2.理論の内容
A.メンガーの理論の特徴
(1) 方法論の特徴
理論科学としの経済学。精密的方法により経済における精密的法則を発見する。
(2) 価値の理論譓蠇蠇消費財の価値
効用物(「人間の欲望の満足と因果連関におかれるもの」)が,財になる条件は,人間
の欲望,この欲望の満足をもたらす物の属性,この物と欲望の満足との因果連関に関する
人間の認識,この物の支配,である。ついで,需求(欲望満足のために必要とする財の数
量)とそれを充足する手段としての財の数量との関係を問題にする。「需求>財数量」の
場合には,その財は希少性をもち,経済人にとってその財は「価値」をもつことになる。
ついで,この価値の大きさを問題にする。このために,欲望の度盛表をつくり,これに基
づいて,限界効用逓減法則および限界効用均等法則を説明している。
(3) 生産財の価値の決定
財秩序という概念を出し,
消費財を第一次財,
これを生産する生産財を第二次財,
さら
にそれを生産する生産財を第三次財・・・とする。そして,
高次財の価値は,
低次財の予
想される価値により決定されると見る。したがって,
生産財(
高次財)
の価値は,
消費財
( 低次財)
の価値に還元して説明できると見たのである。
(4) 交換論
交換の基礎と交換の限界について論じる。交換の基礎は,人びとが欲望の極大満足原則
に導かれて交換を行うことにある。交換の限界は,かれがどの程度交換することが最も合
理的かを決定するという問題であり,交換における均衡点を明らかにする問題である。
(5) 価格論
交換の行われる比率を問題にした。このため,「孤立交換」(双方独占),「独占取
引」(供給独占),および「双方的競争」(完全競争)の三つの場合における,価格形成
を論じた。孤立取引においては,価格の上限は,買い手による商品の主観的価値評価によ
り,その下限は売手の主観的価値評価によって決まる。(例,Aは自分の100
単位の穀物
が,Bのもつ40単位のぶどう酒と等しい価値をもつとみなし,Bは自分の40単位のぶどう
酒がAのもつ80単位の穀物と等しい価値をもつと見る場合には,40単位のぶどう酒の価格
は,穀物80単位と100 単位との間で決まる)。
(6) メンガーの経済学の特徴
限界効用価値論を提出した。消費財のみならず生産財についても,限界効用価値から説
明した。限界効用逓減法則と限界効用均等法則は明らかにしたが,生産論と分配論がない
ので限界生産力説は提起しなかった 。
(2)
ローザンヌ学派
1.代表的理論家とその著作
A.レオン・ワルラス
(Marie-Esprit L on Walra,1834-1910)
『純粋経済学要論』(El
ments d'econmie politique pure,ou th orie de la richesse
sociale,Lausanne & Paris,2 vol.,1874-77)
B.パレート(Vilfredo
Federigo Damaso Pareto,1848-1923)
『経済学講義』(Cours
d'economie politique,Lausanne & Paris,2 vol.,1896-97)
『経済学提要』(Manuale
di economia politica,Milan,1906)
2.理論の内容
A.ワルラスの経済学
(1) 新しい方法と視点の提出
完全な自由競争(
絶対的自由競争) の下での価格形成を問題にし,
それを数学的な方法
によって解こうとした。さらに,
経済的諸量・諸要因の間の相互依存関係をみとめ,
それ
を数理的な方法によって分析しようとした。これが一般均衡分析と呼ばれる。
(2) 経済循環の図式
まず,社会的富を分類し,一回の使用で消滅する「収入」(revenue)
と長期間使用され
る「資本」(capital)
に分類した。資本は,
「土地資本」「人的資本」(
労働力) および
「狭義の資本(
動産資本) 」からなっている。土地は,
土地用役という用役をもち,
地代
という報酬をもたらす。人的資本は,
労働という用役をもち,
賃金という報酬をもたらす。
動産資本は,
資本用役をもち, 利子という報酬をもたらす。
ついで,
経済主体として, 「地主」「労働者」「資本家」の三種類の広い意味での資本
家がおり,
第四の経済主体として「企業家」がいる。前三者は用役の供給者であるととも
に後者の提供する財の消費者である。企業家は,前三者の生産的用役の需要者であるとと
もに,財の供給者である。この結果,地主・労働者・資本家が用役の供給者として,企業
家がその需求者としてあらわれる「用役市場」と,両者の役割の反対になった「生産物市
場」「資本財市場」の三種類の市場が成立する。
地主・労働者・資本家の行動原理は,総効用の極大化の原理であり,獲得した報酬(収
入)の種々の用途への分割の仕方を変更することにより,総効用の極大化,したがって満
足の極大化をはかる。また,企業家は利潤の極大化を原理として行動する。かれは諸生産
用役の結合の比率を変更することにより,その生産物の平均生産費を極小化し,かくして,
利潤を極大化しようとする。
(2) 一般均衡理論の基本構成
ワルラスの理論の課題は,自由競争市場における財貨と用役の均衡価格と,それに対応
する財貨と用役の均衡需要量を,それらを未知数とする連立方程式を立てることによって,
決定することであった。そこで,未知数と同数の方程式を設定する。
ワルラス理論は,四段階からなり,交換の理論(現に存在する財貨と用役が諸個人の間
で消費される際の経済均衡の決定),生産の理論(諸用役の生産的用役と消費的用役とへ
の分割と消費生産物の生産費の決定),資本化およじ信用の理論(固定資本の生産と投資
の問題),流通と貨幣の理論(流動資本とその貯蔵,貨幣の導入)からなっている。
(3) ワルラスの一般均衡理論の特徴
完全競争均衡である。静態であり,単一期間分析である。「長期均衡」分析である。均
衡価格は財の希少性の反映である。完全雇傭均衡である。
(3)
ケンブリッジ学派
1.代表的理論家とその著作
Alfred Marshall (1842-1924)
Principles of Economics, an Introductory Volume,1890.(『経済学原理』)
Industry and Trade,London,1919.(『産業と商業』)
Arthur Cecil Pigou (1877-1959)
The Economics of Welfare,1920.( 『厚生経済学』)
2.ケンブリッジ学派(
狭義の新古典派) による古典学派理論の再構成
アルフレッド・マーシャルを創始者とし,フォクスウェル,ピグー,ケインズ,ロバー
トソン,ロビンソンなどの継承者たちを擁する学派。この学派のもちいた基礎理論は,マ
ーシャルの『経済学原理』(18900年) であり,学派が最も勢力を誇った時期は,1890年か
ら1914年であった。1920年代には,マーシャルの後継者ピグーや,
ケインズ, ロバートソ
ンによって,
飛躍がとげられた。1930年代には,ハロッド,
ジョーン・ロビンソン,
スラ
ッファなどがあらわれ,マーシャルの見解にたいする批判がみられるようになった。
マーシャルは,需要側の要因と供給側の要因の相互作用により,商品の交換価値は決定
されるとみる。そして,需要側の要因としては,
消費者の主観的な満足をあらわす効用を,
供給側の要因には生産者の労働と犠牲を示す生産費をおいた。また,資本や労働などの
生産要素の価格決定つまり分配の際にも,生産側の要因と供給側の要因との相互作用が働
くとみた。
マーシャルは商品の価値を,
市場価格, 短期正常価格,
長期正常価格の三つに分けた。
商品価値の決定にあたっては,
短期的には需要側の要因が大きくはたらき,長期的には
,
供給側の要因つまり生産費がおときく働くとみた。また,収益法則,
内部経済,
外部経済,
代表企業などの概念を提出し,
部分均衡的な分析をおこない,所得分析において業績をあ
げることができた。マーシャルは主にミクロ経済学の基礎を提供した。
[II]
ケインズ革命とケインズの経済学説
1.ケインズ経済学の登場の社会経済的背景
---1929年の世界恐慌をめぐって---
(1) 社会経済的背景
1929年の秋にアメリカのウオール街の金融恐慌にはじまり,全産業に波及し,
さら
に,翌年からはソ連をのぞく全世界に広がった大恐慌が,いわゆる世界恐慌である。1929
- 33年に,欧米諸国の工業生産は50%,貿易は60%,国民所得は50% ばかり減少し,失業者は
1000万以上になったという。この際,
産業恐慌,
農業恐慌, 取引所恐慌,
銀行恐慌などあ
らゆる種類の恐慌をともない,おおくの小企業のみならず独占的な大企業の破産をももた
らし,
資本主義経済体制そのものの危機の様相をとった。それ以後,諸先進国は,
ポンド
・スターリング圏,
ドル圏などのブロック経済の構築をはかり,世界市場の自由な交易は
分断されるにいたった。世界的にみて,
ナショナリズムが強調され,ドイツ,
イタリアで
はファシズムが台頭し,第二次大戦の遠因となった。こうした現実が,
恐慌を一時的現象
とみなし,自由放任主義政策によってそれが解決可能なものとみなす,
当時の主流の経済
学を震撼させた。
(2) 1929年恐慌当時の支配的経済学説の特徴。
宮崎義一氏によれば,すくなくとも,5つの基本特徴があったとされる。すなわち,1)
方法論的個人主義とそれに基づく原子論的社会観,2)
セー法則ないし貨幣数量説に立つ貨
幣ヴェール観,3)
独立生産者的な労働者把握,4)
調和論的景気観,5) 自由放任主義などで
ある。
方法論的個人主義というのは,
当時の経済学説が,
「ロビンソン・クルーソーを経済学
上の主体に想定し,
かれの孤島における行動を分析し,
それを経済行動のエッセンスと考
えていた」ことである。社会は,そうした孤立的な個人の集合と見るのである。貨幣ヴェ
ール観というのは,貨幣は単に実物(
財)
の流れを仲介するものにすぎないとみる見方で
ある。セーの法則(
販路説) にたつ実物分析を重視する見解である。独立生産者的な労働
者観とは,「労働者が職につかないのは,賃金が低すぎて,
労働の限界不効用をカバーし
ない場合か,職業の転換に伴う摩擦的失業の場合に限られている」と見るような見方で
ある。雇用不足による非自発的な失業者の存在を認めない見方である。調和論的景気観と
いうのは,当時の経済学が「調和論的なセー法則を基礎にして,一般的過剰生産の可能性
を理論的に否定」したので,
現実の景気変動は経済外的撹乱か一時的撹乱に過ぎないみる
のである。最後に,
自由放任主義とはなにか。当時の学説は,自由競争が保障されている
限り,
経済はいずれは自動調節的に均衡状態に復帰するとみなし,賃金や利子への政府の
不干渉,
安価な政府と健全財政,
金本位制と自由貿易政策がとられたのである。
2.ケインズ『一般理論』の構造
(レジュメのこの部分の執筆に当たっては,伊東光晴『ケインズ』岩波新書,および宇沢弘文 『ケインズ 「一般理論」を読む』岩波書店等を参考にした)。
(1) ケインズ理論の構造
〔生産物市場(財の市場)〕
(消費性向)
(1)
←- 消費 ← 所得
雇用量
← 生産量=所得←-
資本の限界効率
(2)
←-投資 ←------
〔労働市場〕
(乗数理論)
利子率
←(流動性選好説)
〔金融市場〕
(2) ケインズの資本主義社会観
三大階級
・企業(
法人化された企業,
機械・設備・人的資源からなる経営組織)
・労働者(
労働を提供し,賃金を支払われ,
生活手段を市場で購入する経済主体)
・利子生活者(
金融資産を所有し,
配当, 利子などの支払いを受けるもの)
資本主義的な市場経済とは,企業,
労働者,
利子生活者からなる,
あるいは,
企業と家
計
( 労働者と利子生活者)
の二大部門からなると,ケインズはみる。
(3) 不完全雇用均衡の想定
(古典派の雇用理論との相違)
ケインズ以前の経済学は,
完全雇用状態を前提にし,失業は自発的失業や摩擦的失業の
みを想定していた。しかし,ケインズ以後は,不完全雇用の想定のもとに,
つまり非自発
的失業の存在を前提に,
その理論を組み立てるようになった。
ケインズ以前には,
賃金を引き下げることにより,
雇用を増大し, 失業問題を解決でき
るとみていた。しかし,賃金と雇用との関係をみる場合,
賃金を生産費の一部とみる視点
だけでなく,
賃金を有効需要の一部とみる視点が必要になる。こうして,賃金引き下げ
が,
有効需要を減少させ,生産高と国民所得とを減少させ,その結果,
失業を増大させ
る。したがって,失業問題の解決は,賃金引き下げよりも,
有効需要の増大によると,
か
れはみるのである。
( 図表1.参照
)
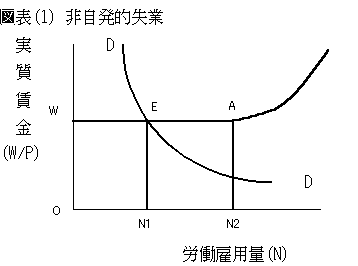
(4) 諸概念の定義
・基本的な単位→貨幣と労働
・期待の概念→短期の期待( 企業家が生産過程をはじめる時点で,
生産過程が終了し,
生
産物を販売しようとする場合,
どれだけの価格と収入を期待できるか)
長期の期待(
資本設備の蓄積をはかるため,
他企業から生産物を購入する
とき,どれだけの収益を期待できるか)
・企業の所得→ある単位期間中に販売された産出物の価値から主要費用を差し引いたもの
( 但し,
主要費用は資本設備に関わる使用費用U
と用役に関わる要素費用
Fの合計)
I = A - (F+U)
・国民所得→
要素費用F は生産要素の所有者の所得だから,
経済全体の総所得は,
Y = A-(F+U)+F = A - U この国民所得
U は雇用水準の決定に重要。
・投資→資本設備の価値が,
単位期間中に, 生産活動を通じてどれだけ増えたか
・貯蓄→所得から消費に対する支出分を差し引いたもの
・投資と貯蓄との関係→貯蓄( 消費者の行動)
も投資(
企業の行動)
も,
ともに,
所得か
ら消費を差し引いたものに等しく,
したがって,貯蓄と投資は必ず等しくなる。
Y ( 所得)
= C(消費) + I(投資) , S( 貯蓄) =Y( 所得) 蠇
C( 消費),
故に,
S ( 貯蓄)
= I(投資) 。
(5) 有効需要の原理
「経済の規模は,社会全体の需要の大きさによって支配されるというのが,ケインズの
有効需要の原理である」(伊東光晴)。なお,総有効需要は,投資需要と消費需要の合計
であり,前者は企業家の投資行動によって決定され,後者は消費者(家計)の消費行動に
よって決定される。企業家は,資本の限界効率(期待利潤率)と市場利子率とを比較考量
しながら投資をする。企業家は予想した利潤率が利子率を上回る限り,
投資を行うもの
と,ケインズは考えている。他方,消費者は,その所得を消費と貯蓄に分割するので,消
費性向の大きさがかれの消費量を決定する。この消費性向は心理法則であるが,その大き
さはある社会において一定していると,
ケインズは考える。
( 図表2
.参照
)。
図表(2) 総需要= 投資需要+ 消費需要
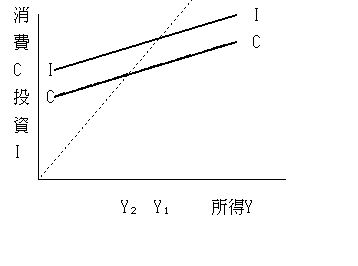
「
N 人の労働者が雇用されている時の総供給額をZ
とし, 総供給関数を,Z=
φ(N) とあ
らわす。また,企業が,
N 人労働者の雇用から期待する収入をD
とし,DとN
との間の関係
を総需要関数
D = f (N)とする。・・・この際,
雇用量は,総供給曲線と総需要曲線と
が,
交わる点に対応する量
Ne で与えられる。この点で,
企業の期待利潤が最大になるか
らである。また,ケインズは,総需要曲線と総供給曲線とが交わる点E
に対応する総需要
を有効需要(Effective
Demand)と呼ぶ。これが雇用の一般理論の要点である」(宇沢,
119p.) (図表3.
参照 )
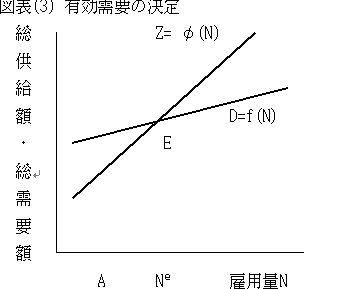
(6) 所得・貯蓄・投資の関係
(消費性向と乗数理論の概念)
ケインズは投資の増加と所得の増加との関連の問題を,
乗数理論によって説明した。
投資の増加と所得の増加との間には,ある一定の比率,
乗数というものがあり,消費性向
が一定の場合,
所得の増加は, 投資の増加の乗数倍になるとみていた。
では,
乗数とはなにか。国民経済において,
投資支出がΔIだけ増加すると,投資財
生産の増加により,国民所得がΔIだけ増加する。限界消費性向(ΔC/ΔY)を Cとする
と,
その結果, C ・ΔI だけの消費需要の増加が発生する。これに見合う消費財生産の増
加により,国民所得はさらにC
・ΔI
だけ増加する。この国民所得の増加は,さらに消費
需要の増加と国民所得の増加〔C
2 ・ΔI
〕をもたらす。このような乗数過程が進行し,
最終的に,
国民所得の変化の総額は,
ΔY=ΔI(1+C+C2
+C3
・・・)=K・Δ
I となる。このK が投資乗数であり,K=
1 /(1-C)=
1 / S という関係にある。但
し,
C は限界消費性向, S は限界貯蓄性向である。例えば,
投資乗数Kが,4の場合,投
資支出が100だけ増加すると,国民所得は400だけ増加することになるのである。
(7) 消費性向( 所得のうちどれだけを消費にあてるか)
消費性向とは,家計の所得のうち消費に当てられる部分の割合である。平均消費性向
(C/Y)と限界消費性向(ΔC/ΔY)がある。また,貯蓄性向とは,所得のうち貯蓄
に当てられる部分である。平均貯蓄性向(S/Y)と限界貯蓄性向(ΔS/ΔY)とが,
区別される。所得は,消費と貯蓄の合計であるから,消費性向と貯蓄性向との合計は,1
である。
〔消費性向に影響をおよぼす客観的要因〕
1.消費は実質所得の関数,
2.消費は純所得の大きさによって決まる,
3.資産価値の変化
が消費性向に及ぼす影響は大きい,
4.利子率の変化は資産価値を変化させることにより消
費性向を変える,5.
財政政策の変化, 6.現在の所得と将来の所得との間の期待の変化.
→
所得と消費を関連づける消費性向はかなり安定的な関数であるが,資産価値の変化や利子
率・財政政策が大きく変化することにより,
変化する.
[ 消費性向に影響をおよぼす主観的要因
]
・消費者の貯蓄動機(1.
予備的動機,2. 深慮,3. 打算,4.
向上,5.
独立,6.
企業(
意欲),
7.名誉心,8.
貪欲) 。
・消費者の消費動機(1.
享楽,2. 短慮,3.
寛容,4.
見込み違い,5.
虚栄,6.
濫費)
・政府や企業などの機関貯蓄の動機(1.
企業の動機--自己資金による投資,2.
流動性の動
機,3.
向上の動機,4. 金融的慎重さの動機)
。
[ 限界消費性向と乗数
]
ケインズ雇用理論の中心であり,消費性向,
労働雇用量,
国民所得,
投資の間にどういう
関係があるか問題にする,
とくに投資の増加がどれだけの国民所得の増加をもたらすか説
明する。ある投資支出がなされた場合,
国民所得の増加は,投資支出の投資乗数倍である
とみる。すなわち,ΔY=k・ΔI,但しk=1/(1-C)=1/S,また,Kは投資
乗数,Cは限界消費性向,Sは限界貯蓄性向。
(8) 投資誘因
(1) 資本の限界効率の決定
資本の限界効率→投資の限界効率と呼ぶべきもの
資本の限界効率は,ある資本-
資産からの期待収益とその供給価格との関係によって決
定される。ある資本-
資産からの期待収益
Q 1・・・Q n の割引現在価値を,
Q 1 /(1+r) + ---- Q t/(1+r)t + ----- Q n/(1+r)n とする。
この際,rは,現在価値を計算するときに使われた割引率である。
いま,その資本-資産の供給価格をPとするとき,資本の限界効率mは,割引現在価値が
供給価格Pに等しくなるような割引率rによって,定義される。
P =Q1/(1+r) + ---Qt/(1+r)t +----Qn/(1+r)n
を満たす割引率rが資本の限界効率である。
( 図表4
.参照
)
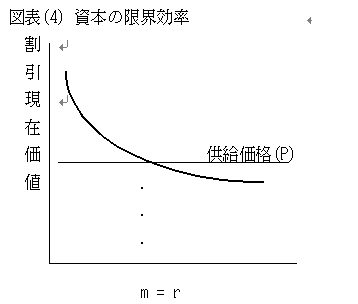
(2) 市場利子率はどのように決定されるか。
(流動性選好と貨幣供給量による) ケインズ以前の経済学は,利子を貯蓄に対する報酬と
捉えるが,ケインズは「利子は流動性を手放すことに対する報酬である」と捉える。流動性
とは, 資産に比べて貨幣がもつ便利さ( たとえば投資のしやすさ) のことである。ひとは所得
をえた場合, その一部を消費し,他を貯蓄する。かれは貯蓄のうちの一部を貨幣のかたちで
保持し, 他を金融資産の購入な どに投資する。この割合を決定するのが, 流動性選好であ
る。ひとびとの流動性に対する選好の強さと,貨幣の供給量とから, 利子率は決定されると
みるのが, 流動性選好説に基づく利子決定論である。
「図表5.において, 利子率
i を縦軸にとり,貨幣のストック量Mを横軸にとる。貨幣保
有に対する需要はLL曲線で表される。利子率は,いわば貨幣保有の価格であるから,利
子率が高くなれば,貨幣保有に対する需要は低下する。流動性選好にもとづいて描かれる
このLL曲線は,図表5
に示すように,右下がりの曲線になる。其れに対して,貨幣供給
量は,利子率の水準とは無関係に決まってくると仮定すれば,縦軸に平行な直線MMによ
って表される。ケインズの言う利子率
ik は,この二つのスケジュールの交点Kに対応
して決定される。そこでは,貨幣保有に対する需要と貨幣供給とが等しくなるからであ
る。」(宇沢,248p.)。( 図表5
.参照
)
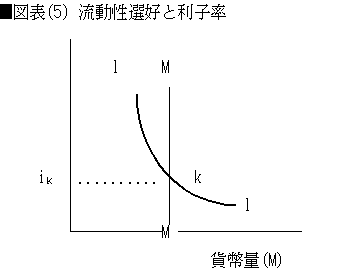
(3) 資本の限界効率と利子率とによる投資量の決定。
「実際の投資は,その限界効率が現行の市場利子率に等しくなるような水準に定まる。
このとき個々の資本財についても,投資率が,将来の期待収益を市場利子率で割り引いた
割引現在価値が,その資本財の供給価格に等しいような水準に定まることになる。この
時,各企業についてみれば,将来期待されるネット・キャッシュ・フローを,市場利子率
で割り引いた現在価値が,投資の供給価格に等しくなり長期的な観点からみて,その企業
にとって最適な投資であるということができる。/
このようにして決まってくる投資は,
市場利子率が高くなれば,投資水準は低くなり,また期待収益が大きくなれば,投資も高
くなる。/
このようにして,投資需要は,一方では,将来の期待収益に依存し,他方で
は,市場利子率に依存することが分かる。」(
宇沢,215p)。
( 図表6.
参照
)
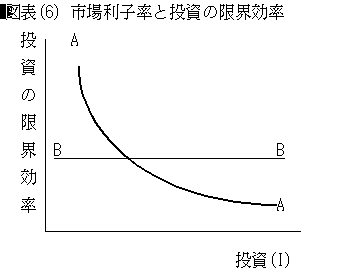
〔Ⅲ〕 シュムペーターの経済学説
(ハンス・H.バス「J.A.シュムペーター入門」参照)
Ⅰ.
シュムペーターの生涯と活動
1883年・・・・メーレン(今日のチェコ)に生まれた
1901年・・・・ウィーン大学に入学
1906年・・・・博士の学位取得(「数学的方法について」)
1907年・・・・イギリスで勉強
1908年・・・・エジプトで政府の財政顧問として活動
『理論経済学の本質と主要内容』を発表。
1909年・・・・チェノヴィッツ大学(今日のウクライナ)の教授
1911/12年・・・グラーツ大学(オーストリア)の教授
『経済発展の理論』(1912)を発表。
1913/14年・・・コロンビア大学(ニューヨーク)で客員教授。『学説と方法の諸段階』を発表。
1914-18年・・・第一次世界大戦
1918年・・・・・『租税国家の危機』を発表
1919年・・・・・ベルリンにて社会化委員会の委員。また、
ウィーンで社会民主党内閣の財務大臣。
1920年・・・・・『今日における社会主義の可能性』発表
1920-24年・・・ウィーンで銀行家
1925-32年・・・ボンの教授
1927―30年・・・ハーバート大学の客員教授
1929年・・・・・世界恐慌
1931年・・・・・日本を訪問
1932年・・・・・アメリカへ移住。ハーバートの教授。
1939年・・・・・『景気循環論』を発表。
1932-45年・・・・ドイツでナチスが支配
1942年・・・・・『資本主義・社会主義・民主主義』発表
1950年・・・・・死亡
1954年・・・・・妻が『経済分析の歴史』公刊
Ⅱ.
シュムペーターの経済学説
1.
動態、イノベーション、および景気循環
l
資本主義経済体制の構造上の特徴――非恒常性、変化、「創造的破壊」。――「資本主義の現実は、最初から最後まで、たえざる変化の過程である。」(『資本主義、社会主義、民主主義』)。
l
1912年に経済的動態に注目。
その思想的源泉――→
マルクスの拡大再生産論、
アメリカの経済学者J.B.クラーク
ダーウィンやスペンサーの進化理論。
l
経済的動態は景気循環の現象と相互関連している。
経済不況=「絶えず新たになされる経済的社会的上昇の必然的な補完物」。経済的変化は経済そのものから生ずる。
l
その理由付け――重要な発明や発見の恒常的な流れが存在。企業家的能力は人口の中に正常分布している。先駆者がイノヴェーションを実現しはじめる。それが成功すると、多くの企業家が模倣し始める。この過程で景気が上昇する(信用膨張、価格騰貴、利子の騰貴)。その結果、イノヴェーションの波が後退する。
l
イノヴェーションの概念
A)
「資源の新しい結合」と定義(『経済発展論』)。
i.
新生産物の製造(=生産イノヴェーション)
ii.
新生産方法の導入(=製造過程イノヴェーション)
iii.
新市場の開発
iv.
新素材の市場の開発
v.
新組織、例えば、独占的地位の創出ないしは独占の破壊。
B)
後の定義=「経済生活の全領域において『〔これまでとは〕別の仕方をとることだ』」(『景気循環論』KZ,92)と定義。
l
イノヴェーションへの融資――→銀行の信用供与――信用は購買力の新創造――企業家に生産手段を購入するための資本を提供。
l
基本モデルの修正――発明は初期のモデルでは外生的であったが、後期には大企業の研究・開発部門に注目し、内生化した。
l
l
経済循環の三つのタイプ
①
短期波動・・・約3年のキチン波動
②
中期波動・・・約8年のジュグラー波動
③
長期波動・・・50-60年のコンドラチェフ波動
(1787-1842年、1843-1897年ブルジョア・コンドラチェフ、1898-1911年の新重商主義的コンドラチェフ循環)(1940-1979年の第四の波動)
l
新シュムペーター経済学におけるイノヴェーション理論の論争
(イノヴェーションの供給側理論。イノヴェーションは過去とのラジカルな断絶か日常的研究の成果か。どのような景気循環においてそれは発生するか。経営の規模とイノヴェーションの頻度との間の関連。)
l
シュムペーター的景気政策は存在するか。
(直接的国家干渉に対する狭い限界づけ。産業政策の父としてのシュムペーター。新シュムペーター的経済政策)。
2.
企業者の理論
l
企業者=経済的進歩の原動力、「資本主義の舞台の主役」
イノヴェーションの担い手、
l
企業=「イノヴェーションの遂行を行うような行為」
l
企業者の定義の四つの側面
①
職業ではなく経済的機能。
②
資本家、経営者、発明者から区別される。(企業者はリスクを負わない)。
③
新古典派の利潤極大化と異なる態度を定義。
④
「企業者」という独自の社会階級は存在しない。
l
信用の意味――企業者はどのようにして資金を得るか。
①
危険な資本を動員すること――この融資形態は軽視。
②
留保利潤――連続的イノヴェーションの枠組み内で強調された。
③
信用融資――特に強調された可能性。
信用=企業者のための新しい購買力の創造
資本=企業者に引き渡され処理されうるある貨幣額。
l
企業者の報酬と利得
企業者は三つの種類の困難事を解決しようとする。
①
新しいことを客観的にはしらないこと。
②
主観的な障害=個人的な抵当を要す。
③
社会的抵抗=外部からの反対の圧力に直面する。
企業者には、かれの革新へのプレミアムとして、企業者利潤が割り当てられる。
l
企業者概念の心理学的および社会学的側面
①
「私的な王国を樹立したいという意志」
②
「勝利への意志」
③
「成功それ自身のゆえに成功をえたいと望むこと」
l
企業家の能力のプロフィル
①
主導権をとる能力。
②
感激させる能力とひとが意欲するものを知る能力。
③
直接的利益への集中を可能にする、ある種の自己限定。
決断を行いうること。
l
現代の具体的な説明
世界的に有名な企業者であるリチャード・ブラウン
ヴァージン・レコード会社の所有者-→ヴァージン・アトランテイック航空会社の再建―→イギリスの鉄道網の購入
l
シュムペーターの企業者像の根源
ニーチェの「権力への意志」や「主人の意志」
ウェーバーの「カリスマ的指導者」
スペングラーの「企業者的な指導的人間」
l
シュムペーターによる企業者概念の修正
第一段階――『経済発展の理論』での見解。
第二段階――企業者の理想化をやめた。行為の動機が高い利得にあると見るようになった。企業者を社会階層とみるようになった。大経営への傾向の中で、技術的革新は企業者の使う技師により遂行される。経営者が工場主に取って代わった。
第三段階――死の直前に、さらに修正。企業者の経済的企業者機能とその社会的類型との分離。企業者は銀行信用よりも自己金融を優先。企業者についてに経験的な確証。
l
現代の経済学における企業者の役割。
①
はるかに広く捉えられるようになった。
②
企業者行動の重要性の減少という後期シュムペーターのテーゼは有効でない。開発途上国や過渡期経済において、シュムペーター的企業家が登場。
3.
経済体制の理論
l
経済体制の定義
①
生産手段の私的所有。
②
営利獲得を目的とした生産。
③
私的銀行による支払手段の創出。
l
時期区分
社会経済体制に占める資本主義的要素の比重に応じて、四つの段階が区別される。
①
ギリシャ、ローマ的な古代とヨーロッパ中世。
②
重商主義の時代(1500-1815年)
③
完全な資本主義の時代(1815-1898年)
④
前世紀の終りから同時代まで(独占的資本主義)
l
資本主義的システムの特徴
このシステムに不可欠な構成要素。
①
情報のメカニズム。
②
短期的な〔資源と労働の〕配置メカニズムと長期的な投資メカニズム。
③
経済的行動を引き起こすための動機のメカニズム。
④
分配メカニズム。
⑤
管理メカニズム。
l
資本主義的システムの長所
①
体制の持つ動機のメカニズム――利得は企業活動を動機付ける。イノヴェーションの実現は一時的独占利潤をもたらす。この動機メカニズムは、不平等なもの。
②
一般的な福祉水準の増大も資本主義の成果。完全競争のもとでは、社会政策は生活水準の向上にとって余計になる。独占化された資本主義もなお活動能力をもつ。
l
資本主義の限界と社会主義の可能性。
『資本主義・社会主義・民主主義』(1942)の中で、論じたが、その論点は三つ。
①
競争的な資本主義に対する自由主義的な賛美。
独占的な実践は、増大するが、それは資本主義の内在的な構成要素である。「完全競争」は、フィクションである。
②
ケインズの資本主義の安定性についての悲観主義的見解。
ケインズの資本主義発展の停滞という悲観主義的な見解を否認――→その根拠=投資の機会には確定した限界がない。貯蓄と投資との固定的な結びつきはない。
③
マルクス主義的な帝国主義論との対決。
シュムペーターは、同情的態度をしめす。生産手段の集中は、外国市場の略奪への関心、外国生産物の輸入遮断、植民地政策をもたらすことを、認めた。
l
資本主義の経済にとっての外在的な限界は何か。
資本主義の歴史的限界――社会的文化的限界とりわけ社会の制度的な構造の変化に存している。
①
ビッグ・ビジネスへの集中は、企業者のタイプを不要にする。
②
資本主義的システムは、自由な経済的決断にもとづくだけでなく、資産と非自発的失業の不平等性にも基づく。
③
資本主義は、生産手段の所有の集中への傾向を、観察した。
④
近代資本主義は、ブルジョウワ家族のための余地を少なくする。
これらの論拠から、「資本主義システムには、自己破壊への傾向が内在している」(『資本主義・社会主義・民主主義』、s.259)。
l
社会主義的経済体制は、機能しうるか。
ハイエクとは異なり、シュムペーターは、社会主義的経済体制が理論的には機能しうるという。
①
ふたつの体制において、需要と供給との法則は、消費財の価格を決定し、その結果、複雑な価格体系を決定する。
②
ふたつのシステムにおいて、効率の指標が、経済的態度を規定する。合理性の原理が根底にある。
l
シュムペーターは反論されたか。
①
社会主義計画経済から資本主義市場経済への逆転が生じた。
② 資本主義のイノヴェーション過程は、うまく機能している――再生力をもつ。
〔マルクス経済学の展開の要旨-帝国主義論争および帝国主義論の類型〕
テキストの『経済学史概説』(ミネルヴァ書房)のなかの,「ドイツ・マルクス主義の展開」
という章,および『ヒルファディングの経済理論』(梓出版社)の第四章「ヒルファディングの帝国主義
観」を,参考して欲しい。
[近代経済学史講義の要旨1╶─╴限界効用学派からケインズまで]
(1)限界革命と限界効用学派
限界革命とは,1870年頃に,メンガー,ワルラス,ジェボンズ等によって行われた,経済学の革新であり,限界効用の概念をもちいて,価値論や分配論などの基礎理論を改革しようとしたものである。メンガーの『国民経済学原理』(1871),ワルラスの『純粋経済学要論』(1874-77),ジェボンズの『経済学の理論』(1871),およびによって,論じられた。かれらの論じた限界効用価値説は,限界効用逓減法則と限界効用均等法則とを含んでいる。
メンガーは,経済学とは精密的方法により経済における精密的法則を発見するものと定義し,消費財の価値を限界効用にもとづき説明しただけでなく,生産財(高次財)の価値も消費財(低次財)の価値に還元して説明できるとみる,帰属理論を提起した。
ワルラスは,完全な自由競争のもとでの価格形成を,数学的な方法によって解明しようとした。かれは,社会的富を収入と資本に分類し,資本をさらに土地資本,人的資本(労働力)および動産資本に分類した。また,経済主体として,地主,労働者,資本家などの用役の供給者と,その用役の需要者としての企業家とを区別した。そして,用役市場,生産物市場,資本財市場の三つの市場を区別した。ワルラスの一般均衡理論は,自由競争市場における財貨と用役の均衡価格,それに対応する財貨と用役の均衡需要量を,それらを未知数とする連立方程式を立てることによって,決定することであった。この理論の特徴は,完全競争均衡,静態,単一期間分析,長期均衡分析,完全雇傭均衡などであった。
ジェボンズは,経済学を数理科学と定義し,それが精密科学として成立するための条件として統計資料の整備をあげた。かれは限界効用価値説を解明しただけでなく,それにもとづいて,交換理論を説明した。かれのこの点での結論は,「いかなる2財の交換比率も,交換が完了した後,消費しうる財の数量の最終効用度(限界効用のこと╶─╴引用者)の比の逆数である」という命題であった。
ジェボンズは学派を形成しなかったが,マーシャルはピグー,ケインズなどの継承者をもつ,ケンブリッジ学派を形成した。マーシャルの『経済学原理』(1890年)によれば,商品の交換価値は需要側の要因と供給側の要因の相互作用により決定される。需要側の要因には効用を,供給側の要因には生産費を置いた。マーシャルは,商品価値の決定にあたっては,短期的には需要側の要因が大きく働き,長期的には供給側の要因が大きく作用すると見た。また,収益法則(収益逓増法則など),内部経済,外部経済,代表企業などの概念を提出した。ワルラスが一般均衡理論を提起したのに対して,マーシャルは部分均衡理論を提出した。マーシャルは,おもにミクロ経済学を論じた。
メンガーに始まる学派がオーストリア学派であり,ワルラスに始まる学派がローザンヌ学派である,マーシャルに始まる学派がケンブリッジ学派である。 問題
(1)限界革命とは何か。また,限界効用価値説,限界生産力説とは,どのような理論か。(2)ワルラスの一般均衡理論とは,どのような理論か。また,その特徴は何か。
(3)マーシャルの部分均衡理論とは,どのような理論か。また,収益法則,内部経済, 外部経済,代表企業などの概念を説明せよ。 (2)ケインズとケインズ革命
ケインズ経済学が登場してきた社会的背景としては,1929年の世界恐慌の勃発にはじまる長期の不況と膨大な失業者の発生がある。こうした状況は,ファシズムやナチズムをうみ,第二次大戦の遠因になった資本主義体制の危機であった。こうした状況にたいして,当時,支配的であった新古典派経済学(ケンブリッジ学派)は,有効な政策を打ち出せなかった。この学派の基本的特徴は,宮崎義一氏によれば,方法論的個人主義にもとづく原子論的社会観,セー法則ないし貨幣数量説にたつ貨幣ベール論,独立生産者的な労働者観,調和論的景気観,自由放任主義などであった。
ケインズ(1883-1946)は,マーシャルの弟子であったが,マーシャルが価格を中心に経済学を構想したのに対して,有効需要を重視し,所得を中心に経済を分析するマクロ経済学を構想した。ケインズ革命とは,このミクロ経済学からマクロ経済学への転換と,需要重視の経済学への転換などを,意味している。
ケインズは,世界恐慌のもたらした失業問題にたいして当時の支配的経済学が対処できないという状況から出発し,不完全雇傭の発生するメカニズムと完全雇傭を達成するためのあるべき政策に関心をいだいていた。そこで,かれの理論の構造は,雇傭量がどのように決定されるかという問題に収斂する形で,構成される。すなわち,一国の雇傭量は,その国の生産量=所得量により決定され,後者は消費需要と投資需要の合計としての総有効需要量によって決定されるとみなし,消費需要と投資需要がどのようなメカニズムによって決定されるかを問題にする。
消費需要は,労働者と利子生活者からなる家計による消費財への需要であり,その大きさは家計の所得の大きさと消費性向によって決定される。つまり,消費者の消費行動により決定される。他方,投資需要は,企業の生産財や人的資源(労働者)への需要であり,企業家の投資行動によって決定される。企業家は,利子生活者から融資された資金を用いて,生産財や人的資源を購入し,企業活動を行う。したがって,かれの投資行動は,資本の限界効率(投資の限界効率)と利子率とを考慮しながら行われる。この資本の限界効率は,ある資本からの期待利益とその供給価格との関係によって決定される。また,利子率は,流動性選好と貨幣供給量によって決定される。
ケインズの不完全雇傭均衡の想定とは,不完全雇傭すなわち非自発的失業者の存在を前提に理論を組み立てることである。ケインズによれば,賃金は,生産費の一部であるだけでなく,有効需要の一部であり,失業問題の解決には,賃金引き下げよりも,賃金増大による有効需要の増大が,有効である。ケインズの有効需要の原理とは,伊藤光晴氏によれば,「経済の規模は,社会全体の中の大きさによって支配されるということ」である。ケインズは,N人の労働者が雇傭されているときの総供給額Zをしめす総供給関数 Z=φ(N)と,企業がN人の労働者の雇傭から期待する収入Dをしめす総需要関数D=f(N)とが,交わる点において,雇傭量と有効需要とが同時に決定されるとみた。つまり,有効需要量を決定する事情が,同時に,雇傭量を決定する事情であることを明らかにした。 また,ケインズは,投資の増加と所得の増加との関連を,乗数理論によって説明した。
消費性向が一定の場合に,所得の増加は,投資の増加の乗数倍になるとみた。投資乗数Kは,K=1/(1-C)=1/S できまるとした。ただし,Cは限界消費性向,Sは限界貯蓄性向である。

